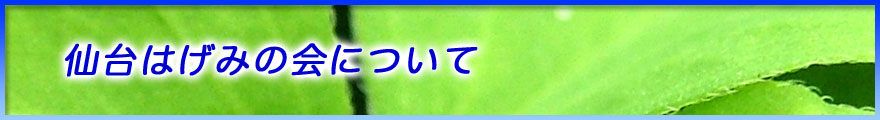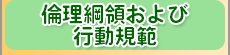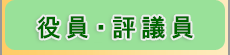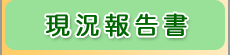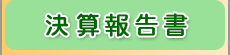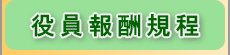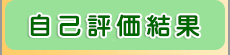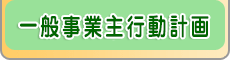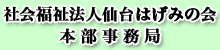2025年(令和7年)新年のごあいさつ
―金野公一さんを偲んでー
皆さん あけましておめでとうございます。令和7年、西暦2025年がスタートしました。年齢とともに時間の経つのが速くなるということは毎年のように言ってきましたが、改めて今年の年号を見て、驚くばかりです。とりわけ若い頃は遠い未来と思っていた21世紀はなんと四分の一近くが過ぎ去ろうとしているのです。
この四半世紀もの間、自分は何を考え、何を成しえてきたのか、そう自問すると、そこには個人に関わる些細な記憶しか蘇らず、そのあまりの卑小さに不甲斐なさが先に立って呆然とするばかりです。でもそれが自分のまぎれもない過去なのです。時間は過ぎ去ることで、その過去を記憶の中に留め、その記憶を生きてきた証とするのです。もしそうだとすれば、いたずらに後悔するのではなく、その証を糧として、今日も明日もまた、何かを成し遂げようとする気概は胸に潜め、些細な現実を生きていく他に道は無いのです。
それぞれがそれぞれの新年を祝っている時にふさわしいことなのか、いささか思うところもありますが、昨年9月に亡くなられた医師の金野公一さんについて少し語りたいと思います。享年83歳。
金野さんは、たんぽぽホームの嘱託医として21年、遠く仙台市心身障害者相談センター(現在のアーチル)の主幹、所長としてマザーズホーム(現在のたんぽぽホーム)の研修会の講師等をしていただいた頃からすれば40年以上、私たちの心の支えであり、私たちの歩みの先を照らし、行く道筋を示していただける存在でした。
同時に私たちだけではなく、この街で子どもの発達に不安を抱えながら暮らしている家族、また生きづらさを感じながら戸惑っている障害者とその家族にとっても、生きる支えであり、未来について語ってくれる存在でした。
金野さんは「たんぽぽホームたより」に「コラム」を120回(10年間)にわたり執筆しています。120回目は昨年の7月。その月には既に覚悟を決められ、ホスピスに移られていました。
最後のコラムの題は「幸せとは」とあり、そこにはこうあります。
「幸せとは、自分に合った居場所を見つけること、という言葉があります。この居場所という言葉、居る場所というだけではなく、仕事や考え方(人生観)また周りにいる人たちにも恵まれているか、などでもあるかもしれません。
また幼児期であれはどのような集団で育ててもらえるか、学齢期に入れば、通常のクラスで学ぶか、あるいは支援クラスにするか支援学校にするか、など本人にあった選択が重要になります。自分の能力に合わせて仕事を選び、余計な気づかいや苦労をしないようにすることや、自分なりの人生観や価値観で、つまり自分の軸で生きていくことを選んで、人生を歩むなどの工夫です。」
少し遠慮がちな言葉ですが、家族や当事者に自分で考えて欲しいという思いが現れているのだと思います。
また115回目の「大事なこと2」というコラムにはこう記されています。
「発達の良し悪しがすべてではなく、如何にして穏やかに暮し易い少年・青年に育て上げるか、を念頭に置きながら、日々の我が子との関わりを考えたいものです。
このありのままの自分で良いのだ、自分の生きかたを肯定し自分らしい生き方、他人の軸(じく)ではなく自分の軸で気楽に生きて行こう、と考えられる人に育てたいものです。特に知的発達にあまり問題のないお子さんの場合は、この自己肯定感を如何に維持しながら、育てて行くかが重要な問題になります。」
金野さんが生涯をかけて求めてきたことがここには記されています。ひとりひとりが自分なりの生きかたを見つけ、それを真ん中(軸)に据えて、自分にふさわしいところで生きて欲しいということです。そのためには、家族、保護者の方々が、本人の能力や感情、行動の特性等のありのままを認め、そのありのままで生きていけるように支援して欲しいということです。それはこうも言えます。知的能力や適応力等で比較して優劣を競う価値観ではなく、誰もが等しく命を与えられて生きているのだという価値観をもって、本人を認めて欲しいということです。
このことを金野さんはこう述べています。
「どのような状態であれこの世に生を受けて生きて行くことが重要なのです。
世の中の役に立つか立たないかは、その人が何をしたかではなく、その人の存在が人の心にどのような影響を与えているかにもよるのです。」(8回 “親が育つとは?” その3)
居場所を見つけるために金野さんが最も大事にしたことは、「穏やかで暮らしやすい少年・青年に育て上げる」ということでした。なぜそのように育て上げなければならないのか、それはそうであれば本人が居場所を見つけやすくなり、幸せに生きることができるからです。他人から指示されたり強制されたりする生き方ではではなく、自分の意思や希望に従って生きて行くことができるからです。また家族、保護者も心穏やかに安心して共に生活することができるからです。
無論そう簡単に「育て上げる」ことはできません。
114回目の「大事なこと1」にはこう記されています。
「お子さんをしっかり育てていくためには、様々な人たちからの指摘や助言が必須なのです。ご家族だけでは気づかないことも多いのが、発達に課題を抱えている子どもたちなのです。周囲にいる人たち、専門的な知識や情報を持っている人たちを頼りながら、わが子にあった育て方を模索していって欲しいとも思います。」
「育て上げる」ということは、家族や保護者の力だけでは、その決意はあったにしても難しいのです。そのためには、家族、保護者と目標を共有し、本人のことを知ろうとし、一緒に考え、助言することのできる人、困難に出会った時、そばにいて、慰め、共に前に進もうと寄り添うことのできる人が必要なのです。金野さんは自らそう語るように、その実践者でした。知り合ったすべての方々のそばに立つことは、物理的には不可能でしょう。しかしその語られた言葉、見せられた、それこそ「穏やか」な表情は、それぞれの記憶として残り、慰めとなり、励ましとなったのです。
医師でしたが、その診断についてこう述べています。
「診断は、ただ診断すればいいというものではありません。本人が今後どのような生き方をして行くか、どのような仕事が合うのか、どうすれば自己肯定的な考え方ができるのか等々様々なことに役立てることが重要なのです。」(111回「大人の発達障害について」)
「重要なことは、その子の将来を見据えながら。その子にあった対応・育て方をし、穏やかで暮らしやすい人柄を育てて行くことを目標にしながら、その子にあった対応を模索していくことなのです。お子さんが、遅れだけなのか、それとも特性を有するタイプなのかを知ることは、適切に対応出来るかどうかの上では、とても重要な視点になります。私は、速い段階での診断や判断が大事なのではないか、と思います。診断が正しければ、その子の特性にあった。その子にふさわしい対応を工夫することになります。」(107回「診断するということの意味は?」)
金野さんは発達や障害が専門の医師です。ですから医師として診断はしますが、その意味や役割をいつも考えていたのです。診療室に留まっていることはあり得ませんでした。幼児から成人までの様々な施設に出向き、その場で診断しました。たんぽぽホームでは、子どもの様子を観察し、家族、保護者とは今までの生活(生育歴)についての情報を共有し、職員(支援者)とは、療育や支援の場での状態について話しあい、その結果を生かして診断がなされました。しかし診断は特性を理解し、特性に合った育て方や支援の仕方を考えるための手段にすぎません。金野さんは何回もたんぽぽホームを訪れ、母親教室等を行い、家族、保護者と共に、「育て上げる」手立てについて考え続けたのです。
金野さんと私は、実は昭和53年(1978年)に知り合いました。その年開所した仙台市心身障害者相談センターに秋田大学医学部から嘱託医として、確か月2回ほど相談と診断のためにお見えになったのです。私は仙台市の初めての心理判定担当(事務職兼務)として配属されていました。金野さんは確か36歳、私は28歳でした。保健師、保育士、教員、ケースワーカ、PT、それに私(その後ST、OTも加わる)という、多様な分野を背負った職員それぞれの発言を熱心に聞き、医師としての気負いもなく意見を言い、そして診断を行いました。職員の質問にも丁寧に時に冗談を交えて応えていました。そのような姿勢はたんぽぽホームでも変わりはなかったと思います。その後私は人事異動で離れますが、金野さんは昭和58年(1983年)に主幹となって相談センターの専属となりました。(昭和60年(1985)から所長)そのころからマザーズホームでは、保護者勉強会や様々な研修等の講師をお願いするようになったのです。その後仙台市の政令指定都市への移行に伴い児童相談所が設置され、相談センターは廃止されました。その時金野さんには転機が訪れます。その間の事情を20回目の「私の今のしごと」というコラムで述べています。
「今のアーチルの前身である仙台市心身障害者相談センターに昭和58年から働き始めたところ数年も経たないうちに平成と時代が変わりこのセンターはなくなりました。新設の児童相談所が小児の部分を引き継ぐことになりましたが私の願いは叶わず保健所に異動を命じられました。結局その後私は平成3年に知り合いの紹介で横浜市の療育センターで働くことになってしまいました。しかし私の気持ちは収まらず大人担当でも構わないからと仙台市にお願いして市の更生相談所というところで嘱託職員にしてもらい月に1~2回横浜市から仙台に通いました。それから今日まで20数年になります。平成14年からはアーチルの嘱託となり今日に至っています、翌年には、横浜市も非常勤にしてもらいたんぽぽホームにも出入りさせてもらいました。」
20回目の便りは平成27年(2015年)に書かれています。「なってしまいました」という書きぶりや「願いは叶わず」「私の気持ちは収まらず」などという心情の吐露から伺われるように、冷静になろうとしながらもそう書かざる負えない、無念さや悔しさが滲み出る文章となっています。金野さんは政令指定都市に移行する時、児童相談所に障害児の担当が移管されることに、強烈に反対していました。せっかく築き上げてきた幼児から成人に至る生涯ケアーが分断されてしまうことが主な理由ですが、同時に政令指定都市になるのであれば、その規模や役割にふさわしい障害児・者に対する医療等の専門性を備えた療育センターを設置するべきだとし、その構想をまとめていたからです。しかしその願いは、まさに「叶わず」でした。構想が受け入れられず、不本意な異動を強いられた仙台市に職員として留まることはできませんでした。多分挫折感のようなものを抱きながらやむを得ず横浜に移られたのだと思います。
しかしそれから14年後、金野さんの願いが正しかったことが証明されるのです。児童の問題が複雑多様になり量的にも拡大し、児童相談所が障害児に十分な対応が出来なくなったことが背景にありますが、改めて生涯に渡る一貫した支援の必要性が認識され、平成14年(2002年)アーチル(仙台市発達相談支援センター)が生涯ケアーを理念とした専門性の高い相談支援機関として設置されたのです。金野さんは、アーチルの発足と同時にその嘱託医となり、その後の経緯は上記の「たんぽぽホームたより」に記された通りです。
その経過には、金野さんの複雑な思いがありながらも抱かざるを得ない、仙台に対する、仙台という地域で暮らす人々への深い思い、愛情を感じます。仙台市の行政に失望して横浜に至りつき、南部療育センター長という仕事を得ていたにも関わらず、仙台にその残りの人生を捧げようとなさったのです。アーチル発足の時。金野さんは60歳を超えていました。ですからアーチルの所長としてお迎えすることは年齢を理由としても「叶わず」だったのかもしれません。でも、もしそうなっていれば、その後の仙台市の障害児と障害者、その家族、保護者への支援がどのように展開し得たのか、より市民の近くにあって、より信頼される相談支援機関となりえたのではないかと、そんな風に思うのです。
また同時に私は思うのです。金野さん自身も医師の枠を超えて仕事ができるアーチルの所長として腕を振るいたかった、そう思ったことが一度はあったのではないかと。その忸怩たる思いがあるからこそ、それを逆にエネルギーとしながら、「たんぽぽホーム」の嘱託医として、とりわけ保護者の支援にあれだけ熱心に、その人生の最後まで没入できたのではないかと。
「たんぽぽホーム」はなぜ存在しているのか。
それは、保護者が「如何にして穏やかに暮し易い少年・青年に育て上げるか、を念頭に置きながら、日々の我が子との関わりを考え」られるように支援する「保護者の居場所」だからです。これが、金野さんが伝えようとし、実践してきたことです。児童発達支援センターとして多様な機能が求められてはいますが、その根幹、根本、芯となるものは不変、不動です。私たちはこの金野さんの生涯をかけて伝えようとしたことを、自らの言葉として、どうすれば実践できるのか考え続け、考え続けなければなりません。そして保護者と共に歩んでいかなければならないのです。
金野さんの思いは乳幼児の保護者にだけに向けられたものではありません。「育て上げる」ことは、成人してからどのように生きて行くのかということの道筋を示すことだからです。障害があったとしても、存在としての価値や意味は全て等しく与えられているのであり、誰もがその人らしく自然に生きて行くことが出来なければならない。金野さんが記した「ありのままの自分で良いのだ、自分の生きかたを肯定し自分らしい生き方、他人の軸(じく)ではなく自分の軸で気楽に生きて行こう、と考えられる人」になって欲しいという言葉は、そのような存在であって欲しいという希望を述べているだけではありません。障害のある成人を支援することの理念ともなることとして、私たちに問いかける言葉です。金野さんは成人施設の嘱託医として多くの利用者の診断や支援を行ってきました、そこで出会った方や保護者から多くを学び、乳幼児と成人をつなぐ言葉として「育て上げる」「自分の軸で気楽に生きる」ということに至りついたのです。
「はげみホーム」、「サポートセンターTagomaru」、「Tagomaruハウス」はなぜ存在しているのか。
それは利用者がありのままの自分を認められ、自分を軸として生きることができるようになる「障害者の居場所」だからです。報酬の改定に伴い、利用者の意志決定を支援することが明確に示されましたが、このことは金野さんが「自分らしく生きる」として目指してきたことそのものであり、時代がやっと追い付いたと言えるのかもしれません。私たちは利用者がその人なりの方法で表す意志を確認し、その意志に従って自分らしく生きていけるように支援しなければならないのです。
各事業の展望を述べる前に長いあいさつになってしまいました。
以下今年、課題となることの項目だけ記します。
1 たんぽぽホームでは、児童発達支援センターとして支援の質を高めていくこと。とりわけ多職種連携の在り方とそれに伴う体制について検討していくこと。
2 はげみホーム、サポートセンターTagomaru、Tagomaruハウスでも利用者の意志を尊重し、支援の質を高めていくこと。
3 はげみホーム(生活介護事業)利用者が地域で生活できるようグループホームの設置について検討していくこと。
5 人材の確保、職員の意欲や能力の向上を図るため、人事評価とも連動した人材育成計画を策定すること。
6 各事業の目的を職員間で共有し、対等な関係を築き、理解と合意を得て執行することで、働き易く、成長できる職場環境としていくこと。
等です。
今年は戦後80年となる年です。世界は、第二次世界大戦後悲惨な戦争を繰り返さないために恒久的な平和を誓い、多くの約束をし、その体制を整えてきました。しかし今その約束や体制を機能不全とする戦争や紛争、専制主義の台頭が世界を震撼とさせています。その状況はここで述べるまでも無いでしょう。金野さんの言葉が意味を持つためには、世界の平和がなければなりません。戦争は最も脆弱なところに犠牲を強いるからです。
最後に、金野公一さんがその生涯を多くの子どもたち、障害のある人々、そしてその家族、保護者へ捧げつくしたことに深く感謝し、哀悼の意を捧げながら、その残された多くの言葉を実践できるよう努めることを誓い、また世界から戦争や紛争なくなるように祈り、そのために何ができるのかを問いながら、新年のあいさつとします。
今年もよろしくお願いします。
令和7年(西暦2025年)元旦
社会福祉法人仙台はげみの会
理事長 細井 実
2024年(令和6年)
新年のごあいさつ
2024年(令和6年)が始まります。
能登半島を震源地とする大きな地震が北陸地方を襲いました。東日本大震災を経験している私たちには他人事とは思えず、心が痛みます。また羽田空港での飛行機事故もあり、新年を、深い悲しみと不安を覚えながら迎えなければならなくなりました。
今年は社会福祉法人仙台はげみの会が設立されてから61年目の年となります。昨年は設立60周年の記念となる年でしたが、法人として特にそのことを意識した行事等を行うことはありませんでした。
時間は無限の過去から無限の未来へと過ぎ去っていきます。そこにいくつかの区切りをつけて、時間をあたかも有限なものであるように今に留めようとするのが私たちの常であるのかもしれません。でもこの瞬間が次の瞬間には過去となり過ぎ去ってしまうのが時間の摂理です。その摂理に対峙して私たちはどのようにふるまえば良いのか。それは永遠の謎でしょう。ただ、過去の上に私たちは存在し、その存在のさらに上に未来を築き上げていくのが、時間というものを知ってしまった人間である私たちの宿命であるということは紛れもない事実です。
そこには時間を区切る節目は無いのです。
それはどういうことか。この瞬間まで生かされることで蓄えられてきた記憶と言う過去を冷静に振り返り、その振り返りを糧として、これからなすべきことを思い描き、未来の自分に向かって、気持ちを高ぶらせて歩んでいくことができるのが、私たちと言う存在だということです。
そのことを、改めて意識させるのが新年と言うことなのかもしれないと思うのです。
昨年の末、ある保護者がたんぽぽホームに入園する時に記した「子どもの様子」という文書に触れる機会がありました。その文書の「なってほしい姿」という欄にはこんなことが書いてありました。
「一人で服を着てほしい
くつ下もはいてほしい
うたをうたってくれたら
絵本を声を出して読んでくれたら
と思います」
多分、たんぽぽホームに子どもを通わせようと思った保護者の多くが似たような願いをいだいているに違いありません。でも、その文字の少しかすれた力ない書き方や言葉少なく区切って連なる文書に、思わず涙してしまいました。子どもの成長に大きな不安をいだき、悲しみに沈みながらかすかな希望をもって、たんぽぽホームに未来を託す母親の姿が目に浮かんだからです。
と同時に別の意味で涙してしまった文章を思い起こしました。それはすでにたんぽぽホームの研修で紹介しましたが、たんぽぽホームの「たより」の「おとうさん・おかあさんのノートから」という欄に掲載されたものです。
「リュックを背負った後、靴下が入っているケースに行って、靴下を手に取って私に渡し、足を出して履かせてとアピール。ただ、それはお姉ちゃんの片足分しかない靴下でした。でもこれを履いたら息子はどうするのか気になったのでとりあえず履かせてみました。すると、片足分しかない事に気づき、靴下の入ったケースの中身を出して探し始め・・・でも見つからず。悩んだ息子は、違う靴下だけど履いているのと同じ水色の靴下を私に渡してきました。右足は水色のプリキュアの靴下、左足はドラえもんの水色の靴下を履き、」
前後を省略していますが子どもの様子とそれを見守る母親の姿は伝わると思います。
この母親は、自分ではまだはけない靴下だけれど、「こうしたい」「こうしてほしい」という気持ちを持ち、それに従って迷いながらも選んできて履かせてとせがむ子どもの姿に、その成長を感じているのだと思うのです。さらに子どもの姿を余裕をもって受け止め、試して見ようとさえ思う自分自身の姿に喜びを見出しているのです。ですからこの文章を母親は嬉々として「おとうさん・おかあさんのノート」に書いたのだと思うのです。そしてこれを読んだ職員もうれしくて「たより」の記事にしたのです。
2人の子どもの成長や発達の様子は違っているでしょうし、家庭環境も異なっているでしょう。私には不明ですので比較することはできないかもしれません。でもどちらの子どもも靴下を一人では履けないし、きっとうたをうたうことも、絵本を声を出し読むこともできないのではないかと思うのです。でも一方の保護者は震えながら、力なく願いを記し、一方は喜んで子どもの姿を見守っている。ひとりの保護者の言葉ではないので、この違いを変化、時間の経過の中で過去から現在へと辿り着いのだと言うことはできないかもしれません。しかしきっと多くの保護者がこのような変化をしているのだと思うのです。
その変化の源はなにか。
それは、たんぽぽホームにたくさんの子どもと保護者が集っていて、その中に参加することができたからです。子どもにはその発達の様子や特性を理解したうえでの支援が、試行錯誤は伴うものの行われていたからです。保護者どうしが語り合う場があり、悩みや不安を話し合うことができたからです。職員が保護者に寄り添い、子どもの理解や子育てについて一緒に考えてくれたからです。そしてありのままの子どもを受け入れ、「家族が子どもの支援者となって助けあって生きていこう」と思い至るからです。私たちの仕事に時間の区切りはありません。支援すべき人たち、支援を求める人たちは、きっと無限にいるのです。そのほんの一部にすぎないかもしれませんが、私たちは、出会った人々に感謝しながら、その人たちの最善を求めて歩んでいかなければならないのです。
令和4年(2022年)に児童福祉法が改正され、児童発達支援センターの地域における中核的な役割が明確にされました。一定の経過措置はあるようですが、この4月から施行されます。国は次の役割を果たすように記しています。
1.幅広い高度な専門性に基づく発達支援、家族支援
2.地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
3.地域のインクルージョン推進の中核機能
4.地域の発達支援に関する入り口としての相談機能
2についてはアーチルとの十分な協議の上で方向性を定めていくことになるでしょうが、それ以外はすでに実践されていて、たんぽぽホームの仕事に大きな変化は無いと思います。既に発達支援や家族支援の専門性は備えていますし、保育所や幼稚園と地域で協働していくことで、インクルージョン推進の役割は果たしています。また初歩的でありますが保護者や子育て機関からの相談も受けています。ただ、一つだけ強調しておきたいことがあります。それは、いままで積み重ねてきた実践の目的や方法を、再度確認し、それらを保護者や地域の子育ての支援者が、更には地域の方々も理解できるように、また容易に説明できるように言語化するということです。このことは従来から求められていることですが、改めて児童発達支援センターとしての自覚に基づき行わなければなりません。言語化し「なぜこのような支援をしているのか、どうやって支援したらよいのか。」を常に問いながら日々の実践に勤しむことが必要なのです。
はげみホーム、サポートセンターTagomaru、Tagomaruハウスの成人の施設では昨年人材育成委員会を立ち上げ、現状における様々な課題とその取り組みの方向性を議論してきました。まだ検討途中ではありますが「法人が求める職員」として次のことが示されています。
1.専門性を高め、より良いサービスの提供ができるよう、仕事を通じて自己成長できる人。
2.相手の立場を理解し、協調性をもって積極的に対人関係が構築できる人。
3.チャレンジ精神をもって、新たな発信と行動力を持ち、様々な改善や提案ができる人。
4.福祉を担う人材として適切な倫理観を持ち、模範となる人間性が求められる。
「自己成長」、「協調性」、「チャレンジ精神」、「人間性」と盛りだくさんと思われるかもしれませんし、そんな完璧な人になれるはずはないと批判されるかもしれません。しかし、利用者と対等な存在として交流し、支援していくために、また職員どうしが協力して利用者と向き合っていくためには、どれもが望まれるものでしょう。肝心なことは、目指すべき姿が示されることです。それが明らかになれば、道筋はそれぞれ異なっていても、共通のゴールを目指し協力しながら歩むことができるからです。多分そこには、辿り着くべきゴールテープは無いかもしれません。でもそれを目指して、歩み続けること、日々努力し続けることこそに、働くことの、更には生きることの意味があるのです。
今まで、施設の中では、運営方針や利用者への支援等を巡って様々な議論を積み重ねてはきました。またグループホーム開設や施設の経営改善のプロジェクトを設置した経験はありますが、施設横断的に、法人の根幹にかかわる課題について深く議論し、その成果をまとめることはしてこなかったように思います。様々な課題や疑問が法人や施設の運営についてあったにもかかわらず、個人の思いや施設内のこととして留めてしまっていたとするならば、法人として深くは反省しなければなりませんが、今回職員が人材を巡って喧々諤々と議論し、その成果をまとめようとしているのです。児童発達支援センターにおいて実践を言語化する必要性について述べましたが、議論の成果をまとめるということも、言語化するということであり、成果を誰もが理解し我が事として実行できるようにするために必要なことなのです。人材育成委員会の成果は職員像の提起にとどまるものではありません。それに向けた課題の整理や改善の方向性も素案には示されていますが、更に議論を深め、組織としてやるべきこと、個々人が取り組むこと、優先すべきことなどの整理やそれに基づく実施計画のようなものも必要になるでしょう。また、人材育成委員会の意味は、その成果にあるだけではありません。その過程において職員参加で意見交換がなされることで、様々な議論を通して職員が自己研鑽への意欲を持ち、上記3の「新たな発信と行動力を持ち、様々な改善や提案ができる人」へと成長する契機になっていくからです。
昨年から法人の経営会議が発足しました、ここには成人施設だけではなくたんぽぽホームの代表も加わり、相互理解を進めながら法人の課題を幅広く検討していくことになっています。
会議体が乱立して業務の支障をきたしては意味がありませんが、枢要な課題についてはしっかりと議論する場として必要なものですので、多くの職員が議論の場に参加できるよう努力していきたいと思います。
生活介護施設であるはげみホームの経営、収支の状況が厳しいものとなっています、この傾向は国の経営実態調査などでも明らかですが、それでも全国的にはまだ相当程度収支差額は黒字となっています。一昨年には経営改善員会を設置して検討しましたが、更なる努力が必要でしょう。利用者の確保や実態に合った障害区分の見直しを求めることによる収入増を図るとともに、利用者には魅力的であり、職員には働きやすくなるように業務内容が適正化され、同時に合理的な支出となるような道を見出していかなければなりません。まさにそのためにも、職員一人ひとりが自らの課題として考え、議論していく風土を築き上げていく必要があるのです。
サポートセンターTagomaru、Tagomaruハウスではようやく経営は安定していきました。昨年のあいさつで詳しく述べましたが、グループホーム単独での収支で黒字となることはあり得ません。利用者の状態に応じホームヘルプ事業を行いその収支差額で補填することで収支相償となっているのです。
4月からの報酬改定ではこの「個人単位の居宅介護等の特例的取扱い」が維持されることとなっていますが、本来はグループホーム利用者の障害の状態や介護の体制にあった人員体制の適正化とそれに見合った報酬の設定がなされなければなりません。国は「基本報酬について、重度障害者の受け入れなどのサービスの支援内容の実態や調査結果を踏まえた見直し」(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について 令和5年12月6日)と言っていますが、限られた財源をやりくりするなかで、どこまで実態に即した改定になるのか。財務省は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について「改定率は全体で+1.12%(国債162億円)とする。なお、改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果があり、それを合わせれば改定率+1.5%を上回る水準となる。」(令和6年度社会保障関係予算のポイント 令和5年12月)と、何か自慢げに(?)記しています。一般歳出が7.5%も伸びる中で、1.5%程度の増加では重度障害者への重点配分がなされるにしろ、根本的な見直しは難しいでしょう。与えられた資源をさらに有効に活用し、工夫しながら事業経営に努めていくことが肝要なようです。
ただ、はげみホームの利用者の今後のことを考えた時、地域での生活の場となるグループホーム事業の拡充は避けて通ることのできない課題です。厳しい経営状況や建設価格の高騰していることを考えると容易ではありませんが、それこそ職員の議論による工夫や、保護者の方々の理解と協力をも求めながら、実現する方策を見出していかなければなりません。
昨年の12月18日にNHK で「塩の行進、ガンジーの志を継ぐ者たち」と題された番組が放映されました。「映像の世紀」というシリーズの一つです。その中で、マーテイン・ルーサー・キング・ジュニアの「わたしには夢がある。(I have a dream)」と題された演説が紹介されていました。彼が、キング牧師と呼ばれ、わずか39歳で凶弾に倒れるまで、暴力に頼ることなく人種差別の撤廃を訴え続けたことは誰でも知っているでしょう、またこの演説もあまりにも有名です。改めてこの演説の全文を読んでみました。演説は、奴隷解放宣言がなされたにもかかわらず、以降の100年の間、黒人は自由を奪われてきたという現実を語り、でも、私には、「『すべての人間は平等につくられているということは、自明の真実であると考える』というこの国の信条を、真の意味で実現させる夢」があり、その夢をかなえるという信念を抱いて行動しようと訴えるものでした。(信条とは独立宣言のこと。)
黒人と白人が平等に暮らすということについて語られ列挙される夢の一つにこのようなものがありました。
「私には夢がある。それはいつの日か、あらゆる谷が高められ、あらゆる丘と山は低められ、でこぼこしたところは平らにならされ、曲がった道がまっすぐにされ、そして神の栄光が啓示され、生きとし生きる者がその栄光を共に見ることになるという夢である。」(アメリカンセンターHP)
語られる夢は、人種差別がなくなり、すべての人びとが平らでまっすぐな道を、平等というまっすぐな道を行くことができるようになるという夢です。平等は人種の間だけに求められるものではありません、生きとし生きるものとあるよう。あらゆる差別や格差、それゆえの不条理な現実に置かれているすべて人びとに求められているのです。
そう思うとき、私たちがなすべき、またなしている仕事、障害者福祉の仕事とは一体何なのか、その目的とは何かということに気づかされるのです。
発達の道筋は多様であり、どのような発達の道筋をたどろうともまた異なる発達の状態にあろうとも子どもの間にも、保護者の間にも差別はなく、平等なのだということ。その平等を実現するために、子どもの特性に応じて発達への支援をし、保護者の苦悩に寄り添っていくことが、たんぽぽホームの使命なのではないか。
成人の施設を利用している人たちにとって、平等の意味するものは更に明確でしょう。障害者と呼ばれ続け、その特性や個性を理解されず、生きづらさや不如意な生活を強いられていると感じること、思うことは、多分誰もが経験しているのに違いありません。そのような彼らが平等に暮らせるように、その意志を尊重し、特性や個性に応じて生活の支援をしていくことが、はげみホームやサポートセンターTagomaru、Tagomaruハウスという成人施設の使命なのではないか。
キング牧師の死から56年、法律は整備され、公的な場での人種差別はなくなっているかもしれませんが、経済的な格差の拡大や白人至上主義の顕在化などによって、いまだ苦悩は続いています。いや昨今の度重なる人種を巡る争いを見れば課題は深刻になっているとさえ言えるでしょう。
障害者への差別も国連による「障害者に関する権利条約」の各国での批准が進み、制度面での差別解消は更に進んでいくでしょう。しかし、彼らの一人ひとりが、十分に社会の一員として平等に受け入れられ、自由に生活できているのかと言えば、その答えはノーでしょう。
私たちの歩むべき道に行きつく先があるとすれば、社会の側の様々な障害が取り除かれた、差別のない社会、平等に暮らせる社会であると言っても、過言ではないでしょう。
新年のあいさつとしては、少し課題が大きすぎたかもしれません、毎日の歩みは目的に比べればあまりに小さく、短いものでしょう。
でも確実に一歩でも前進しなければならないのです。
今年は「辰」の年です。訓読みでは「とき」とも読むようで、字義はまさに時間ということのようです。改めて法人の過去に思いをはせ、その上に未来を築きながら、時間について考える年なのかもしれません。
深い悲しみと不安を覚えながらの新年の始まりですが、そのことを心に刻みながら、でも私たちは歩んでいかなければなりません。
皆さんのご支援とご協力をいただき、少しでも前進できる年となるよう努力してまいりたいと思います。
今年もよろしくお願いします
令和6年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会
理事長 細井 実
2023年(令和5年)
新年のごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。
令和5年、西暦2023年が始まります。
あまり公言していませんが、今年は法人設立から60年という記念すべき年です。社会福祉法人として認可されたのは平成10年(西暦1998年)で、まだ25年ですが、財団法人として認可されたのが昭和38年、西暦1963年なのです。
もう一昨年となりましたが、当時、たんぽぽホームの指定管理者選定審査委員会での私の発言は次の言葉から始まりました。
「私はいつも新規採用職員にこう言うことにしています。
『半世紀以上も前、昭和38年(1963年)に、学校に通うことも許されず、家から出ることも難しかった障害のある子どもたち。そのお母さんたちが、せめて同じ悩みを語り合い、子どもたちを遊ばせる場所が欲しいと始めた運動。その力によって生まれたのが、皆さんが勤め先として選んだこの法人です。当時の彼女たちにとっては荒野のようなこの街に、やっと灯すことのできた明かりでした。その光をともし続け、さらに輝いて街中を明るくしていくのが、君たちの責務です。』
初めての明かりはマザーズホームと言い、今は、今回審査をいただく5つの施設(立町、大野田、田子西、上飯田、西花苑)に昨年審査いただいた袋原を加え6か所のたんぽぽホームという明かりとなっています。」
60年というこの法人の歩みは、毎日の実践の積み重ねです。60年ということ自体に何か意味があるわけではありません。でもこの長い歴史によって積み重ねられてきたものの上に今があるということは忘れてはならないでしょうし、またその一番の基底には、この法人は「この街にやっと灯すことのできた明かり」であった、初めての灯であったという事実があることを常に反芻し続けなければならないと思うのです。
それはどのようなことがあっても、「障害のある人とその家族、保護者の側にあり、その歩む道の足元と歩む先を照らすことのできる灯となれ。」と言うことを私たちに、この法人に指し示しているのです。
特に節目だからといって特別のことをするつもりありません。
改めてこの法人に課せられた使命、役割の重さを感じながら、またかけがえのない利用者と保護者の方々との日々の出会いを大切にして、「灯」となれるような実践、支援を積み重ねていきたいと思います。
今年予想される大きな変化は、今まで厚生労働省の所管であった障害児の事務が、4月1日に設置される政府の新しい組織である「こども家庭庁」に移ることです。あくまで組織の問題であり事務の所管が変わるだけで、政策が大きく変わることは無いでしょう。
ただ政府の公表された文書ではこう言っています。
「全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいながら共に生きていく共生社会の実現に向けて、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点等を踏まえ、こども家庭庁が所管する子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を行う。」(こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について 令和3年12月21日閣議決定)
今までは障害者施策の一部としていた障害児の施策をインクルージョンの視点からこども支援施策の一部として行うというのです。この視点の変化は、施策の前提となる「在り方」に大きな変化を及ぼすものと思います。
確かに児童福祉法の立場からすれば障害児施策は児童福祉の一部であることは今でも言えるとも思います。ただ現実の施策としては、「障害」という一生続く事実に対して、幼少期から成人にいたるまでどのように支援するのか、そして、社会の一員として自立していくためにはどのような支援が必要かという視点から推進するというのが基本的な考え方でした。そのため障害者総合支援法等を整備し、児童、知的障害、身体障害、精神障害などに区分されていた障害者施策を一元化してきたのです。それは障害のある個人に着目し,その特性に応じた生涯にわたる支援を行い、その支援をとおして、障害があっても尊厳を持った個人として尊重される社会を形成していくということです。
一方、障害の有無にかかわらず、ともに生きる「共生社会」を実現するためには、障害者に対する支援だけでは難しく、社会の側が障害者の自立を支え、ともに在ることを当たり前のものにしていく「共生社会」へと変化していかなければなりません。そのためには、障害という事実にのみに注視し障害者を支援していくだけでは不十分で、社会そのものを変化させる施策が必要なことは言うまでもないでしょう。障害者への差別や虐待を禁止する施策などはそのために整備されてきました。ただそれでもやはり「障害」と言う事実に社会はどう向き合ってくれるのか、どう変わってくれるのかという、障害者の目線から「ただす。」ような施策であったと言えるでしょう。
今回の政府の方針は、もしかしたら、そのような現状を半歩でも変革していくものかもしれません。それは「障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点等を踏まえ」とあるからです。このことは子どもだけの問題ではありません。障害者が自立していくということは、地域社会の一員として、まったく平等に包摂され、障害者だからとか、障害があるからと特別に扱われることなく社会活動に参加できることだからです。障害者の側が自立や参加を当たり前だとして主張しても、地域社会の側も呼応して同じ主張をしなければ「共生社会」、個人の努力や熱意、同情や憐れみを超えた「共生社会は実現しないのです。
そのためには、「子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を行う」という今回と同じ考え方が、青少年施策や成人、老人などへの無数の施策においても実現することが必要だと思います。障害者への施策が、他の様々な施策の中に包摂され、それぞれの施策において障害者への支援と社会参加の道筋が示されるようになるならば、障害者のみを対象とする「障害者福祉」施策は必要なくなるかもしれないのです。もちろん特性に応じた固有の施策はなければなりませんが、それは各分野で必要とされる多様な個別の配慮の一つとして行われれば良いのです。
このような期待は、私の思いにすぎないのかもしれません。また、いままで「障害」という事実への支援、それも生涯にわたる支援のために積み重ねてきた施策の、体系ともいえるものを壊すことになり、支援の後退になってしまうという考えは尊重されなければならないでしょう。ただ体系は体系として残すにしても、その実現の方途は、障害者施策という特別な分野だけでなされるのではなく、他の様々な分野において「障害」という事実への支援がその一部となり、それぞれの分野で実現されていく言うのが、「共生社会」の在り方でないかと思うのです。
でもやはり、今まで子どもから成人まで総合的に切れ目なく支援できるように取り組んできた障害者施策から、子どもだけが特別な存在として切り離されてしまうのではないかという憂慮があります。
政府も先の「基本方針」で「その際、文部科学省や厚生労働省と連携し…中略…切れ目ない支援を充実する。医療的ケアが必要なこどもや様々な発達に課題のあるこども等について、医療、福祉、教育が連携して対応する環境整備を進める。」と続けて記載しています。縦割りと言われる行政組織においてどこまで実現できるかは不明ですが、それぞれの担当が十分議論し「障害児」「障害者」でまさに切れ目のない支援ができるようにしなければなりません。
前置きが長すぎたようです。
児童発達支援センターであるたんぽぽホームも「こども家庭庁」が国の所管官庁となります。ただ仙台にはアーチルが(仙台市北部・南部発達相談支援センター)があり、「生涯に渡る、切れ目のない、一貫した支援」を設置目的としているので、仮に行政の担当部局が変わったとしても、支援の継続性は保たれるでしょう。
同時に、子育て支援施策の中で障害児への支援がなされることで、大きな利点が生まれるようになると思います。
たんぽぽホームでは令和元年から「就学前療育支援推進事業」を市から委託を受けて実施してきましたが、昨年より当法人だけでなく市内の9か所の児童発達支援センターが市内を3ブロックに分かれて実施するようになりました。事業は、幼稚園や保育園に通っていて発達や行動が気になっている子どもの保護者に、主に子ども理解に向けたグループワークを行う「初期支援プログラム」と、乳幼児を抱え子どもの発達に不安を抱える在宅の保護者に、育児の振り返り等によって子どもへの理解を促す「ペアレントプログラム」の2つです。
「初期支援プログラム」では、幼稚園や保育所と協働して子どもと保護者の相談に応じ、子どもの特性に沿った保育や幼児教育がなされ、保護者への支援も行われていくことが望ましいと考えています。また「ペアレントプログラム」においては、発達や育児の不安について同じ悩みを持つ保護者どうしが初めて出会う場であり、その場に参加するためには、母子保健での相談や子育て支援機関での相談からの導入が望ましいと考えています。
しかし、現状では幼稚園や保育園との協働や母子保健、子育て支援機関との連携がなされているとは言い難い状況があります。無論たんぽぽホームの努力が足りないのかもしれませんが、子育て支援の分野と障害児支援の分野が分かれていて、子育て支援から障害児支援への橋渡し役が存在しないということも大きな原因だと思っています。
今後、障害児の地域社会への参加と包容(インクルージョン)を進めるために、障害児支援を子育て支援の中で行うという政府の方針が仙台市の行政に浸透すれば、このような状況は改善されて行くことが期待されます。地域の子育てを支える機関の一つとしてたんぽぽホームが新たに位置付けされることで、幼稚園、保育園、子育て支援機関,母子保健機関などと協働していくことが、今までよりも容易にできると思うのです。
ただ同時に、子育て支援を支える様々な機関の協働の対象となり信頼を得ていくためには、それらの機関にスーパーバイズできるような療育支援と保護者(家族)支援の専門性を高めていかなければなりません。
また、児童発達支援センターには、地域での障害児支援の中核としての専門性がガイドラインや厚生労働省の諮問機関での検討で求められています。どこまでその機能を果たすかは、仙台市にはアーチルがあるので、アーチルとたんぽぽホームの役割分担と協働の議論を深めていかなければなりませんが、少なくとも療育支援と保護者(家族)支援の専門性を高めることは、どのような状況になったとしても必要となるでしょう。
サポートセンターTagomaru は、令和元年の開所以来、収支の赤字が続いてきましたが、令和3年度の決算ではほぼ収支相償となり、少なくとも単年度の経常経費だけを見るならば経営は落ち着いてきています。主な要因はグループホーム入所者で障害が重く、個別支援計画にその利用が位置づけられ、市が認めた場合に利用できる居宅介護(ホームヘルパー)を積極的に利用し、利用者の支援の質を高め、居住しやすさを求めてきたことが、結果として収入の確保につながったということです。昨年の7月には20名の定員までの入居がなされ、法人による家賃負担が逓減したことも影響しているでしょう。またショーステイの利用者の確保に努力してきたことも寄与しているものと思います。夜間勤務や入浴、身体介護などの困難な仕事を積極的に引き受けてきた多くの職員の熱意、それらを効率的に采配してきた管理職員の努力。何よりも、施設を棲家として、一時的な宿泊場所などとして喜んで利用してくれた障害のある仲間たち、そして、センターを信頼してわが子を託してくれた保護者の方々に、心より感謝しています。
ただこれで安心することはできません、直接的には新型コロナウイルス感染症によりショートステイが休所を余儀なくされたり、グループホームでも一時的な帰宅をお願いしたりで、迷惑をかけましたが、センターとしてもその分収入が減るので、経営状態にも良くない影響が現れるものと考えています。
そもそもグループホームは人件費などに見合った給付費が算定されておらず、単体では経営は成り立ちません。居宅介護の収入で補っていますが、この制度は令和6年までの経過措置となっています。根本的な制度の改善が必要ですが、厚生労働省は重度化への対応に具体的方針を示していません。
障害者の地域社会での自立のためには、グループホームは無くてはならない存在です。これからも、施設数は増大していくでしょう。国や市が、とりわけ障害の重い方がその特性にふさわしい手厚い支援を受けられるよう給付費などの見直しと拡充できるかどうかに、障害者の将来が託されているのです。
ただ、国や市の動向とは別に、法人としては、次のグループホームの設置について検討しなければならないと考えています。法人全体の経営状態からどれだけ資金調達が可能かどうかによって時期は決まるかもしれませんが、はげみホームの利用者とその保護者のニーズに応えることが責務だからです。
はげみホームの実施している生活介護事業は、かつての知的障害者通所更生施設が障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)の施行によって移行したものであり、その歴史的な経緯のためか比較的安定した制度となっています。収支も黒字が見込めるものであり、法人の経営に寄与してきました。サポートセンターTagomaruの開所以来の収支差もはげみホームが時間をかけて積み上げてきた積立金があったからこそ補填することができたのです。ただここ数年の経営を取り巻く環境は厳しくなっています。多数の要因があるとは思いますが、基本的には給付費の額が人件費などの増大に追い付いていないことです。また障害の等級判定が年々厳しくなっているようで障害程度が現状より軽くみなされる事例が増え、その結果給付費が減額されるという事態も起きています。
生活介護事業は、どれだけ重い障害があっても通うことのできる日中の居場所であり、様々な活動によって生きていることを実感できる場所でなければなりません。そのためには支援の質と量を低下させることはできません。ただ現状を直視すれば今まで以上に効率的で効果的な運営、経営をしていかなければなりません。そのためには職員の効率的な配置や支援の在り方などの見直しに積極的に取り組んでいく必要があると考えています。
60年と言う歴史を次の時代に引き継ぎ、新しい歴史を創っていかなければなりません。そのため最も必要なことは、事業を担うべき人材の確保とその育成です。人があって初めて歴史は引き継ぐことができ、更に発展することができるからです。
たんぽぽホームでは療育支援と保護者支援の専門性を高めることが求められていると言いました。サポートセンターTagomaruでは、夜間勤務や入浴、身体介護などの多くの困難を引き受けた職員の熱意に触れました。はげみホームでは、職員の効率的配置や支援の在り方の見直しが必要であると記しました。どれも人材に係るものです。
広く介護や福祉の職場での人材不足が指摘されています。ただ、法人としてはむろん十分にとは言いませんが、職員の待遇向上や資格取得支援、各種研修の実施などに努力してきました。現在、たんぽぽホームでは、人材育成委員会を設置して、経験年数に応じた標準職務表を作成し、それに基づいたOJTを含む研修計画の見直しを進めています。サポートセンターTagomaru では、IT ツールを生かしたオンライン研修の実施や情報の共有を図っています。はげみホームでは人材育成委員が発足しました。たんぽぽホームに倣って職務の標準化や体系的な研修計画の作成などを計画しています。今後とも、職員との真摯な協議をすすめ、人材の確保と育成に必要な方策の検討と実施に努めていきたいと思います。
考えるべきこと、計画すべきこと、準備すべきこと、実施すべきことが限りなくあるように思います。それを明らかにし、順序だてて実施し成果を出していかなければなりません。
新年のあいさつとしては長すぎ、またあいさつと言う枠からはずいぶんはみ出しました。
今年は「卯年」です。「卯」は漢字源と言う辞書によると「門を無理におしあげて中に入るさまを示す。」とあります。今年、私たちにはどのような門が待ち構えているのか。それを無理にでも通ることができるのか。楽しみにしながら、皆さんと共に歩んでいきたいと思います。
ウクライナへのロシアへの侵略戦争には出口が見えません。新型コロナウイルス感染症にも終息の気配は見えません。世の不都合と不条理に対して、私たちはどう向き合うのか、どう生きていくのかがまた問われる年となるようです。
今年もよろしくお願いします
令和5年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会
理事長 細井 実
2022年(令和4年)
新年のごあいさつ
2022年、令和4年がスタートしました。昨年は心から喜んで「おめでとう」とは言えないという嘆きの言葉からこの挨拶を記していましたが、今年もその心境には変わりはないようです。
新型コロナ感染症が、新しいオミクロン株へと変質し、世界では猛威を振るっています。我が国では落ち着き始めたような素振りをしていましたが、その猛威を避けることはできず、いずれ大流行が来ると言われています。それにも拘らず、人々は外出し、人込みを生み出し、感染症が人と人の接触で拡大することを忘れたように行動しています。既に3年目を迎えるこの感染症が今年はどのようになるのか、想像することさえ困難です。
また世界では、政治体制を巡って民主主義が危機に直面しています。民主主義の根本は個人の自由の尊重であると思います。それは現代にいたる社会が様々な支配の構造を経験し、その反省の上に築いてきたかけがえのない政治体制です。でもただその制度を当たり前のものとして軽視し、守る努力を怠れば、時代は後戻りしてしまうという現実に私たちは出会っています。政治は国家を支配する権力を生み出しますが、権力は国民が民主主義体制によって委任したものであり、国民に自由を保障し、国民が何時でも奪うことの出来、国民によって支配されたものでなければなりません。しかし世界ではその逆の独裁や権威主義によって国民を支配する国家が急増しています。また中国をはじめ国民の自由を奪う弾圧や虐殺も繰り返されています。民主主義と権威主義の対立が今後どのように推移していくのか、人類は民主主義を至上の価値として守り、広げていけるのか、不安を拭い去ることはできません。
感染症と権威主義が私たちの世界を脅かしています。その不安と恐怖から逃れることができるのか、そして自由で平安な日常を取り戻すことができるのか、あるいは得ることができるのか。今年がそのために前進する年となるのか、後退してしまう年になるのか。
昨年法人の施設管理者と副施設長、主任、副主任の職にある職員だけではありましたが、法人の課題について意見を求めました。Word A4 での提出でしたが、数ページにわたって記されたものもあり、全員が真摯にまた熱心に法人改革の意欲を示していました。具体的にそれらの意見をどのように生かしていくのか、更なる意見交換が必要です。ただ今日の段階で、恐れずに大要を紹介するならば以下のようになると思います。
一つは、人材育成への取り組みを充実しなければならないということです。障害福祉事業には人間性と専門性のどちらも求められています。自己研鑽に励むのは当然としてもそれを支援する環境が求められますし、職場研修と外部研修が合理的に結びついた研修計画が必要となるでしょう、そして何よりも職員一人ひとりが目標を持つことができ、その目標を達成しえるような人材育成計画を法人として確立しなければなりません。
二つは、職員間のコミュニケーションが十分に図れるような職場環境となって欲しいということです。職場は多様な職員から構成されています。お互いが理解し協働して業務を達成するチームワークが必要です。また上司の適切なリーダーシップも求められます。法人や施設の方針、利用者の支援計画等について共有できる会議や協議の場と時間が確保されなければなりませんし、自由に意見交換できる健全な人間関係を築く全員の努力も必要です。
三つは、法人や施設経営の中長期的な視点が必要であるということです。組織体は日々の業務をこなしていけば良いというものではありません。今の業務が法人や施設の将来にとってこのような役割を果たしているのだという自覚を持てれば、職員の意欲も高まりますし、自身の将来への展望も持てるようになります。さらに目標達成に向けて取り組む一体感や帰属意識が高まります。そのためには将来に向けた法人の事業展開や経営改善の方向性を少なくとも今後数年にわたって示す事業計画を作成することが求められます。
その他にも法人の基本理念の確立、運営効率の向上のための経営感覚の必要性、施設長、副施設長、主任の役割明確化とりわけ主任業務の改善、職制の在り方と処遇の適正化、正規職員と臨時職員の業務の在り方、成人施設と児童施設の交流と相互理解、会議の役割や開催方法等々、数え上げればきりがありませんが、貴重で前向きな意見が示されました。どれも重要な課題ですが、日々の個人の努力だけで解決できるようなものは少ないと思われます。法人として議論を積み上げ、何にどのように取り組むのかということを具体的に明示していくことが必要でしょう。
法人もまた各施設も常に業務は道半ばであり、常に改善の努力を積み上げていかなければなりません。昨日よりも今日、今日よりも明日と少しでも法人も施設も職員も成長していくのです。留まってはいけないのです。そのためにこれらの意見を生かしていきたいと考えています。
サポートセンターTagomaruは間もなく開設4年目に入ります。以前から何度も指摘しているように経営は安定していません。グループホームでは令和4年度中に定員20人に達する入居を目指しています。入居予定の利用者がスムーズに入居できるよう最善の努力をしなければなりません。それぞれの特性や性格に合った快適な生活ができるよう支援計画を作成し、それが実施できる体制を準備することが必要です。そのためには支援の質を確保できる職員が充足されなければなりませんが、介護職員の全国的な人材不足から逃れることはできません。
昨年も述べましたが、夜勤を伴う臨時職員の給与に、月給制の導入や賞与の支給、年度毎に昇給する給料表の作成等の改善を行い、求人をしていますので、ぜひ職員体制が整うよう願っているところです。
また支援の質を確保するためには、入居者の介護の度合いに応じてホームヘルパーによる支援が必要になります。これも円滑に行える体制を整えなければなりませんが、やはり人材確保が課題となっています。登録ヘルパーの求人と法人職員の資格取得も進めていきニーズに答えられるようにしていかなければなりません。
国はグループホームにおける重度障害者の受け入れ態勢の整備を課題として、重度加算の拡充等を図っていると言っていますが、必要な職員体制と十分な給与を保証できるように給付費の見直しを行わない限り単独での経営の安定は不可能です。他の事業所からの繰り入れやホームヘルプ事業の収入で補う努力をしていますが、それには限界があります。国や仙台市でも課題を認識し、基本的かつ抜本的な給付と補助の見直しをしていただきたいと思います。
田子西たんぽぽホームで仙台市の委託を受け行ってきた「就学前療育支援推進モデル事業」は、大きな見直しが進められています。当初モデル事業は、乳幼児健診の後指導や子育て支援事業で気づかれた発達に不安のある子の保護者にグループワークを行う「ペアレントプログラム」と、保育所や幼稚園で発達や行動等が気になっている子と保護者が共にたんぽぽホームに通い、子どもは療育的な係わりを持った支援を受け、保護者は子の理解に向けたグループワークに参加する「併行通園」の2事業を行うことになっていました。
しかし「ペアレントプログラム」では保健所や子育て支援機関からの紹介が円滑には機能せず予定した参加者を得ることができませんでした。「併行通園」については、子どもをたんぽぽホームに通わせるには給付制度の利用が必要であるとの判断がなされ、ただ気になるとか不安であるとかだけで通うことが難しくなってしまいました。
「ペアレントプログラム」は、たんぽぽホームに通う以前の早期の段階で子どもと保護者に出会う事業であり、「併行通園」は、たんぽぽホームに係わることなく保育所や幼稚園に通う子どもと保護者に出会うことの出来る事業です。法人しては、たんぽぽホームが就学前の子どもと保護者に切れ目のない療育支援と保護者支援を行う場として、飛躍的に発展することができる機会である考え取り組んできました。この思いには変化はありません。
「ペアレントプログラム」については、母子保健や子育て支援と協働していくという姿勢を今後も強く推し進めていくことが必要であると考えています。そのためにはモデル事業で得た保護者や支援者からの高い評価を関係機関と共有するとともに、事業を普遍的なものとして母子保健の後指導や子育て支援の一環として公式に位置づけ普及していくことが必要です。
「併行通園」は保護者に対する「グループワーク」だけを行う「初期支援プログラム」に変わることになりますが、保育園や幼稚園との連携がなければ子どもの発達には結びつかないでしょう。児童発達支援センターとなることで強化された地域支援事業では、保育園や幼稚園で気になる子の相談を受けることが大きな柱となっています。今後複数の地域で地域相談員が参加して「モデル事業」を行う方針が市より示されていますので、地域相談員による訪問や相談と「初期支援プログラム」による保護者支援が相互に影響しあい、保育所や幼稚園とも協働して行われていくことが必要です。
冒頭、新型コロナ感染症と専制主義について記しましたが、障害福祉の在り方を問う問題でもあると考えています。それは支援者と利用者の距離の取り方の問題であり、自由とは何かの問題です。
コロナ禍で学んだのは、感染を防ぐためには接することを避けなければならないということです。しかし支援者は利用者と接しなければ支援はできません。ただ、支援者だけの判断で利用者に近づき過ぎていなかったかを考える機会を、コロナ禍が与えたのではないかと思うのです。まず利用者に向き合い、その意思を確認し一呼吸おいてから係わり接していく。それは利用者の意思と人権を尊重することになるからです。
また専制主義から学ぶことは、支援者が利用者に対して専制的にふるまっていないかということです。支援者の言うことをよく聞き、ただおとなしく従う者を良いと思い、そうでない者は問題あると思う。それで良いのかということです。保護者に対しても同じです。支援者の専制的、支配的な振る舞い、考え方が利用者や保護者の自由を侵し従順であることを強制しているに過ぎないかもしれないからです。
さて、今年もたくさんの課題に取り組まなければなりません。今年一年で解決できるような課題は少ないですが、日々の実践と思索にしかそれを克服する道は無いでしょう。
職員一人ひとりの自覚と協働、利用者の活動、保護者の支援がなければその糸口をつかむことさえできません。
今年は「寅」年です。寅の字義は「家の中でからだをのばして、いずまいを正すこと」(漢字源)とあります。改めて自分のすがたかたちを顧み姿勢を正すことが求められているのかもしれません。
法人が今年も地域での役割を果たせるよう「いずまいを正し」て祈念し、「新年のあいさつ」といたします。
今年もよろしくお願いします。
令和4年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会 理事長 細井 実
2021年(令和3年)
新年のごあいさつ
令和3年、西暦2021年がスタートしました。
「おめでとう」と言うべきなのでしょうが、素直にそう言い切ることはできそうにありません。それは東日本大震災の後に迎えた年の思いに重なります。
世界は新型コロナウイルス感染症の災禍に怯えています。不安と焦燥を抱えながら私たちは新年を迎えることになりました。いくつかのワクチンの接種が始まっていますが、何時この災禍から人類は逃れ得るのか先は見通せないままです。文明はそれまで分散し孤立していた人類が他者に出会い、言葉を交わし、認識を共有し、共同して働くことを発見したことで始まりました。でも感染症は人と人が接触することで拡大します。それは共有や共同というこの人類社会の根源を脅かす病であると言えるでしょう。
また昨年は”Black Lives Matter" を掲げた社会運動が、この社会に人種や民族や宗教などの差異を理由とする差別や偏見が、深くそして根強く存在していることを明らかにしました。なぜ差別や偏見が生まれるのか、その答えを得ることは簡単ではありませんが、人権思想を得た私たちは差別や偏見を超えて、すべての個人が平等であり、自由を希求できることを社会の普遍的な価値としてきました。しかし昨年の様々な出来事は、その価値を大きく揺るがすものでした。
このような時代にどうしたら私たちは「おめでとう。」と言えるのか。
私達が関わる障害者福祉の世界において問題はさらに深刻であると言えるでしょう。
感染症は人と人が近づくことを忌避しますが 障害のある人を支援するためには近づくことこそ求められています。介護の現場は、身体的に触れあい、言葉をかけ、支援者と利用者が理解しあい信頼しあうことで成り立っています。グループ活動でも利用者同士が相互に認識しあい様々な共同作業を行うことで成長していくことをめざしています。むろん一人ひとりの状態は異なるので接触や言葉かけ、相互関係の濃淡は異なりますが、それぞれに合わせた“触れあい”によって支援をしなければならないのです。
障害のあることは人間の差異の一つではあります。障害者福祉の目的は社会の側がすなわち社会の普遍的な価値の側が障害ゆえの差異を克服してゆくことにあります。障害のある人が克服していくのではありません。市民の人権に対する価値観、障害があっても平等であるための社会環境(法制度、経済政策、都市計画等)、地域生活の支援などが社会の側に求められているのです。人種や民族のような対立や抗争を引き起こしてはいませんが、潜在化している障害者への差別や偏見は依然として存在し、そのことを障害のある人は生活のしづらさ等として実感しているのです。
今年は改めて、新型コロナ感染症の感染対策を徹底したうえで、“触れあい”を基本とした支援活動をどう行うことができるのか、皆で知恵を出し合い工夫しあって実践していかなければなりません。まずその前提としては、職員一人ひとりが社会の基本を支える、無くてはならない仕事に従事しているという認識を持ち,個人としての感染予防対策を徹底していかなければなりません。そのうえで職場の対策を十分行い、工夫された支援に取り組んでいくことが必要です。
また私たちの仕事は障害ある人の支援を行うことですが、それは障害という差異のために差別や偏見を受けることのないように社会を変えていく仕事でもあるという認識を、改めて持たなければなりません。地域社会での自立を多くが目的としてあげますが、自立とは社会の普遍性の中に身を置くということであり、人権が尊重され、平等に扱われ、自由を求めることが出来るということです。むろんただ言葉を並べただけで実現できることではありませんが、障害があるが故の不条理や理不尽さに出会ったならそのことを訴え、共に生きるためにはどうあったら良いのか考えていかなければならないのです。
さて法人にとっての課題を2つだけ上げたいと思います。
一つは一昨年に開設したサポートセンターTagomaruの経営を安定させることです。
田子西地域に世代を超えた交流拠点として設置された”ノキシタ”(交流施設、レストラン、保育所、サポートセンターからなる複合施設)の一部であり、単独では実現困難な事業の創造に先駆的に取り組んでいます。ただ障害者福祉施設としてだけ捉えるとその経営は安定しているとは言えません。その大きな要因はグループホームやショートステイの夜勤を伴う職種や短時間となるホームヘルパーの人材確保が順調ではないということです。給付費で経営していくためには人件費の支出には限界があり臨時職員も採用しなければならないのですが希望する方は多くありません。夜勤を伴う職種には臨時職員であっても月給制の導入や賞与の支給、定期昇給等の待遇改善の努力をしているところです。
またグループホームの定員は20人ですが現在9名しか入居していません。職員体制の不足に加え、利用候補者の入居への準備に時間を要していることなどがその理由ですが。早期に定員に達するようにしなければ経営は成り立ちません。利用希望者の声を聞きながら、入居候補者を決め計画的に準備を行っていく予定です。
また昨年仙台市が一部の事業を除きレスパイト事業を廃止したため、サービスが低下しないようショートステイで日中の支援もできるようにしました。しかし利用者数は思ったほど増えてはいません。ホームヘルプ事業でも利用者数が大幅に計画に達していません。やはり職員体制が整わないことが主な理由ですが、更なるニーズの掘り起こしを行い利用者の増大にも努めなければなりません。生活介護事業の利用者や保護者の皆様には、生活の質の向上をはかり、家族が安心を得ることが出来るこれらの事業を積極的にご利用いただき、そのことを通してご支援いただきたいと思っています。
二つは児童発達支援センタ-となったたんぽぽホームの役割を明確にしていくことです。
すべてのたんぽぽホームが児童発達支援センターとなってから2年8か月が経過しました。各ホームには地域相談員が配置され、地域とどのように関わっていくのか試行錯誤が今も続いています。また一昨年の10月から田子西たんぽぽホームでは仙台市の委託受けて「就学前療育モデル事業」を行なっていますが、ペアレントプログラム、併行通園ともに参加者数が計画していたより大幅に少なく、見直しが迫られています。
発達に不安のある就学前の子供たちと保護者に対しては継続して一貫した支援が必要ですが、そのためには出産から就学までに関わる様々な機関がそれぞれの役割を明確にし、協力をしていくことが必要です。保護者とってもそれぞれの役割と協力関係が良く理解できることで、安心して支援を受けることが出来るのです。むろんこのことは今に始まった課題ではありませんし様々な努力がなされてきた課題です。ただ福祉サービスが多様な機関で実施されるようになるに従ってそのたびに見直し点検をしていかなければならない課題だと思います。
児童発達支援事業所が児童発達支援センターとなったとき、その役割と他の機関との協力の在り方について十分に議論されてこなかった、あるいは理解されてこなかったことが、いまだ十分な成果を上げていない理由であると思います。むろん各ホームは色々工夫をして子育てに関係する機関との連携をはかり、地域での認知度を高めるとともに子供たちや保護者の支援に取り組んでいます。ただそのことがどのような役割を持ちどれだけの成果が期待されているのか明確でないため、試行錯誤が続いているのです。
モデル事業においても参加した子供と保護者にはポジティブな変化が表れています。しかし期待した乳幼児健診の後指導からの参加やアーチルによる紹介等がスムーズにはいかず少数の参加となっています。新しい事業なのでやむを得ないことかもしれませんし、乳幼児を抱える保護者に事業に参加するよう動機付けることは簡単ではありません。ただ、なぜ児童発達支援センターがこの事業に取り組んでいるのか、学齢前の療育においてどのような役割を果たし、どれだけ重要な取り組みであるかが関係機関の間で十分に理解され、協力しようという意志が明確に示されていれば、また違った状況になっていたに違いないのです。
このような課題に私たちの法人だけで取り組むことはできません。地域の就学前療育に責任を持つ行政が積極的に関係機関の多様な意見の調整をはかり、市民にもわかりやすい形で各機関の役割と協力の関係を示し、その体制を構築していかなければなりません。仙台市には「アーチル」という全国に類を見ない専門機関があります。また「保育所」や「幼稚園」での障害児の受け入れという長い歴史もあります。また各区には「保健福祉センター」があり、「子育てふれあいプラザのびすく」もあります。しかしそれぞれが過去の歴史の上にとどまっていては、とりわけ多様化する発達障害への対応や、孤立し複雑な課題を抱えた保護者や家族へのケアーに積極的に関わっていくことは困難です。
今後、児童発達支援センターを運営する他の法人とも協力して このような課題について仙台市に問題提起を行い、協議をしていきたいと考えています。
今年は丑年です。“漢字源”によると「手の先を曲げてつかむ形を描いたもので。すぼめ引き締める意を含む」とあります。
新型コロナウイルス感染症の災禍の下で、少しでも感染の拡大を抑えていくことが人類の課題となっています、だとすれば「引き締める」ということは私たちが感染症と闘う上での考え方や行動の支えとなる言葉のように思えます。日常において行動を「引き締め」制御し、不要不急の活動等を「引き締め」」抑制していくことが感染予防対策として必要であると説かれているように思えるからです。
今年もまた難しい課題に直面しています。職員一人ひとりがまさに気と身を「引き締めて」、また法人が一丸となってその克服に向けて前進しなければなりません。
ぜひ皆さんのご支援とご協力をいただきたいと思います。
今年が良き年になるよう祈念する。その意味でやはり「おめでとうございます。」という言葉を最後に綴りたいと思います。
今年もよろしくお願いします。
令和3年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会 理事長 細井 実
2020年(令和2年)
新年のごあいさつ
皆さん、あけましておめでとうございます。
西暦2020年、令和2年が始まりました。令和初めての新年でもあり、昨年のように時代の行く末についての言説が巷間を賑わすことでしょう。とりわけ今年はオリンピックイヤー、パラリンピックイヤーであり、スポーツを通じて高揚された国民意識や、国を超えた選手間の交流や友情への称賛がこの国の空気に充満することでしょう。同時代を生きているものとしてこのような空気に触れ、巷間の言説を耳にしながらこの国や世界の在り方について今一度考えを至らせる良い機会かもしれません。
昨年の漢字は「令」でした。これは令和の「令」が選ばれたということでしょうが、昨年の台風を経験したこの地域にとっては少しばかり違和感を抱く漢字でした。「令和」の英訳を政府は「Beautiful Harmony」としています。だとすれば「令」は「美しい」という意味になります。でも昨年のこの地域は美しかったのか。10月12日、テレビは「命を守る行動をとってください。」「今まで経験したことのない大雨が降ります。」という警告を繰り返していました。しかしまさに経験したことのない豪雨によって、川の水は堤防を越え、地面にしみ込んだ水は山稜を崩し、多くの命が奪われ、数えきれない家屋が倒壊し浸水したのです。失われた命への慟哭が響き、悲しみが、耐えられないような悲しみが地を覆いつくしました。私たちは同じような経験を8年前にもしています。なぜ同じ地に災禍が繰り返されねばならないのか。なぜ多くの無残なそして不条理な死に私たちは立ち会わねばならないのか。その答えはありません。誰も答えてはくれません。残された者はただ言葉を失い絶望の淵に立ち尽くすことしかできません。でも私は思うのです。半途で断たれた生の全うすれば果たせたかもしれない人生は、残された私たちに託されているのではないかと。残されてあるということは奪われた命の代償として生かされているということだはないかと。だとするならば、私たちは、死者によって生かされているのであり、そのことに謙虚でなければならず、それを始点としてどのように生きていくのかを考え抜いていかなければならないと思うのです。
今年の法人の最大の課題は昨年開設したサポートセンターTagomaruの運営を軌道に乗せることです。その使命は地域で暮らす障害にある方とその家族の自立を支えていくことです。自立とは、まさに自ら立つことですが、障害があるが故に抱える不如意があるとすれば少しでもそれを軽減する手立てを講じながら自らの力で暮らしていくということです。障害のある方が自立してくためには、まず本人を含めた家族が自立して普通の暮らしをしていかなければなりません。家族が安心して暮らせるようになってそこから本人が自立に向けて歩みだすことができるのです。それは家族から自立することが自立の始まりであるということです。また家族にとっては、障害のある方から家族が自立することでもあるのです。それは本人と家族が依存しあうのではなく相互に自立し支えあうことを意味しています。障害が重ければ重いほど自立生活は難しいかもしれませんが、でも家族に依存して生きていくのではなく沢山の支援者に力を借りながらでも、やはり家族から自立し本人主体に生きていくことが必要なのです。家族関係が多様化し抱える問題も複雑化していて一概にそうすべきだと言い切れることではないかもしれません。でも顕在化している深刻な事件を目の当たりにして改めて自立の必要性を感じるのです。この施設は相談事業やレスパイト、ショートステイにおいて、障害のある方の家族に潤いと安心をもたらしその営みを十全になすことができるように、また本人が自己に目覚め自立への動機づけがなされるように支援していきます。またグループホームとホームヘルプにおいて、障害のある方が共同生活ではありますが、その分効率的に多くの支援者の介助や介護を得ながら、自己の意思が尊重されることで居心地の良さを感じられる暮らしができるように支援していきます。ただまだ開設から日が浅いためもありますが、その機能を十分に果たしているとは言えません。
特に利用希望者のニーズに十分こたえられるだけの人的体制が確保されていないのです。これは福祉労働をめぐる恒常的な課題でもありますが、オープンヴィレッジ「ノキシタ」を構成する魅力的な職場環境であることや複合施設として多様な職種や人材が相互啓発しながら働けることなどを積極的に訴えるとともに、地域との交流を深め近隣に住まいの方にとっても魅力ある働きやすい職場であることを示すことで人材の確保に努力しなければなりません。関連して期待した収入を得ることができず、このまま放置しておけない深刻な経営状況になっています。このためには職員の一人ひとりがその状況を理解したうえで、日々の業務の在り方を点検し、全体と個々人の目標を立て、Plan Do Seeを確実に実行していかなければなりません。克服する力はチームワークにあるのです。障害の状態や家族おかれている場所や抱える課題はそれぞれ異なります。その異なった状況にきめ細やかに対応していかなければなりません。「言うは易く行うは難し」です。経験の積み重ねも必要でしょうし、当然職員の研鑽が求められます。その上経営問題にまで対処することは大変かもしれませんが、事業の質の向上を図りながら、収入の確保を図っていくことは職業として支援者を選んだ以上責務でもあるのです。
たんぽぽホームでは昨年10月から仙台市の「就学前療育支援推進モデル事業」を受託し実施しています。事業はペアレント・プログラムと併行通園の2つを行うことです。前者は「保護者がアーチルに相談することにためらいを感じることで適切な療育支援につながることのできていないケース」に「保護者の子供に対する否定的な視点を肯定的に変え」「児童の状態に合わせ必要に応じてアーチルに繋げていく」ことを、後者は「保育園・幼稚園における集団生活の中で」「療育支援の必要な児童が存在するが」そのような児童と保護者を対象に「現在の保育所等の利用と併行して児童発達支援センターに通所してもらい」「子供や障害に対する理解を深め」「適切な療育支援の利用に繋げていく」ことを事業内容としています。
*「 」内は仙台市が提示した委託仕様書より引用
一昨年から児童発達支援センターとなったたんぽぽホームには地域相談員が置かれ、通所してくる児童と保護者の支援に加え、地域との関わりを強めていくことが求められています。ただ現実には関係機関とのネットワークを形成し地域の課題について問題を共有することにとどまっています。関係機関を訪問し相談を受けてはいますが積極的に地域のセンターであるとして市民からの相談を受ける状況にはなっていません。地域相談の必要性は理解しつつも看板を出すまでは時間がかかるという認識でした。そのように思案しているときこの委託事業者が公募されたのです。この事業は私の思案に方向性を与えるものだと思えたのです。地域相談員の活動の中で聞かれる声は「アーチルにつながってはいないけれど気になる子供や不安を抱えている保護者」にどう対応したらよいかということでした。それは幼稚園や保育所に在籍している子供だけではなく、のびすく(子育てふれあいプラザ)や子育て支援センターを訪れる子供とその家族に対しても言える悩みであったのです。より身近なところで子供と家族に出会い保護者の子供理解を助けていくことで早期の療育に繋げることは地域相談の役割です。また幼稚園や保育園に在籍する子供を、保護者と保育士との共通の理解の下で療育に繋げていくことも関係機関への支援でもあり地域相談の役割です。これら二つの役割をこの事業は果たすものであり、たんぽぽホームが現在実施している就学前の子供への療育にこの事業が加わることで、出生から就学までの「気になる子供と不安を抱える家族」に対する支援を切れ目なく繋げることができるのです。まさに児童発達支援センターが地域の療育を担うことになっていくのです。幸いペアレント・トレーニングは宮城野区と若林区の「のびすく」を会場として実施することができました。今後は保健福祉センターの乳幼児健診の事後指導教室や、会場となった「のびすく」の子育て支援活動との連携を図り、より早期に保護者の気づき促しこの事業へとつないでいくことが必要でしょう。併行通園は田子西たんぽぽホームで実施しています。保護者の信頼も厚く成果を上げつつありますが、短期の実施であり、母体となる幼稚園や保育園等と連携し終了後のケアーについて積極的に関わっていかなければならないでしょう。モデル事業ということで今後検討すべき点がたくさんありますが、児童発達支援センターが地域相談にさらに踏み込み、アーチルとの役割分担を検証しながら、地域で暮らす子供とその家族、保護者の支えとなる契機となればと思い事業の着実な実施に努めていきたいと考えています。
先に死者に生かされてあるということを言いましたが、私たちの仕事は障害のある方とその家族によってあり得ているのです。そのことに謙虚に向き合い真摯に日々努力していかなければなりません。
今年はネズミ年です。ネズミは子という字を当てています。子は字義通り子供のことであり新しい命が萌し始めるということです。いずれも昨年からの事業について述べてきましたがどちらもまだ命が萌し始めたばかりです。今年はぜひ少なくとも無事に誕生日を迎え更なる成長を祈願できるようになって欲しいと思っています。
今年もよろしくお願いいたします。
令和2年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会 理事長 細井 実
2019年(平成31年)
新年のごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。
西暦2019年、平成31年が始まります。今年は平成最後の年であり、新しい年号が始まる年でもあります。
平成の時代を振り返り、その歴史における役割や功罪などについての言説が巷間にあふれています。またそれは新年号のもとで始まる時代への期待と不安を示す言説となっています。確かに年号が一つの区切りとなって過去を振り返り、その反省と悔恨を基として未来への決意や希望が語られることには意味があると思います。しかし、私達が法人の責務や役割として求めているものは、年号によって左右されるものではありません。日々の実践の場において、反省や点検を行い、常に改革と前進を目指すことが求められているからです。その様な不断の営みとその積み重ねによってはじめて未来へと至ることができるからです。
無論、時代の大きな転機を契機として、己を振り返り、なにかしらの変化をしていくことを否定するものではありません、ただそのような転換が仮にあるとしてもその根拠は、日々の実践を通して感じること、思い至ることの中になければならないということです。
今年は「亥」年です。動物では「猪」があてられています。「漢字源」によると猪または豚の骨格を縦に描いたもので骨組のこと、またその骨組が出来上がるという意味があるそうです。あえて言えば、新年号で始まる時代に、新しい骨組を組み立てねばならないという意味で「亥」年は最もふさわしい年であると言えるかもしれません。ただ骨組みは今年だけで組み立てられるものではなく、さらに骨組に肉付けし衣を着せられるようになるには、時間で区切れない不断の努力こそが求められるでしょう。
今年は法人にとってまさに「亥」年にふさわしい新しい骨組を組み立てる年となります。
長い間切望しながら踏み切れずにいたグループホームが開設される年だからです。障害者支援の目的は「地域で自立しひとりの市民として安心して生活できるようにしていくこと」にあります。今まで法人では生活介護事業を行ってきましたが、それは日中活動の場を提供するものでした。しかし生活とは日中活動だけで成り立っているわけではありません。生活とは生きていく時間、そのすべてを意味しています。どこまで関わるかは利用者の状態によって一人ひとり異なるでしょうが、その生きていく時間の中で生み出される生きづらさや不如意を少しでも減らし、ごく普通の生活ができるように関わっていくことこそが障害者支援の意味するところです、そのためには日中だけではなく、食事し入浴し睡眠する、そして起床し食事をするという夕方から朝までの生活にも寄り添って支援していくことが必要なのです。グループホームはその様な支援を実践する場として設置されます。
利用者の生活を支えるということは法人にとっても大きな成長の礎になります。それは今まで見えなかったものが見えるようになることであり、解かりづらいこともあった利用者の考えや行動の理解を深めることでもあるからです。それは法人の障害者支援の質をより深いものとし、支援者一人ひとりの利用者への関わりを本人の意思に沿ったものへと向上させることにつながるでしょう。
グループホームにとって必要なことは3つあると思っています。
ひとつは「居心地の良さ」と言うことです。生活の場として快適であり、家族から離れた利用者が不安や不便を感じることなく安心して暮らせるようにしなければなりません。
ふたつは「孤立してはいけない」ということです。利用者が市民の一人として尊重され、近隣に暮らす方々と日ごろから交流し、理解と信頼を得て共に生きていけるようにしなければなりません。
みっつは「自立した生活ができる」ということです。利用者の尊厳が守られ、本人の意思に寄り添った介護や介助を受け、充実した日常が得られるようにしなければなりません。
法人とっては全く新しい事業が始まることになります。無論数多くのグループホームがすでに設置されており、学ぶべき先例を吸収しながら実施していくことになりますが、当法人では平成30年度から制度化された「日中サービス支援型」という事業を行います。これは障害の程度が重く、毎日は生活介護事業所などに通うことが難しい利用者をも受け入れ、グループホームにいながら昼間も様々な活動を行えるようにするものです。法人の生活介護事業では障害が最も重い利用者を特別な体制を組んで支援しています。その様な利用者であっても生活できるグループホームを設置したいと考えているからです。
その実践には今まで経験したことのないようなことが求められるかもしれません。しかし法人としてはその様な経験こそが法人と職員の質の向上を図る絶好の機会を捉え、障害が重くとも孤立することなく、自立した生活ができる、居心地の良いグループホームとなるようにしていきたいと思います。
6か所あるたんぽぽホームは昨年4月に児童発達支援センターにすべて移行しました。その目的は昨年も述べましたが「地域へ関わりを強くすることにあります」。ただ行政や他のセンターを設置する法人との十分な議論が成されないまま、移行することが優先されたきらいもあり、その新しい業務の骨格はこれから組み立てていかなければなりません。
発達に不安のある子供たちとその家族の地域との関わりを考えたとき二つの方向性が考えられます。
ひとつは「現在の状況に応じて関わる方向」です。不安を抱えたまま孤立し、専門機関に関わることにはためらいのある家族の心を開き、子どもへの理解を促し、支援をうけることができるようにしていくということです。また支援に繋がったとしても家族の置かれた現実に向き合いその状況に応じた最適な支援ができるようにしていくということです。そのためには、ためらいを感じることなく訪問でき、思いを打ち明けられるようなセンターにならなければなりません。また様々な相談機関、専門機関などとネットワークを形成し多様なニーズに応じた適切な対応ができるようにしなければなりません。
ふたつは「成長するのにつれて関わる方向」です。出生から学齢へと成長していく過程で、家族は様々な不安やつまずきを経験し、子供の抱える発達に関わる課題も常に変化していきます。その一つ一つに寄り添い継続的で一貫した支援ができるようにしていくということです。そのためには、成長に応じて関わっていく医療機関、保健所、保育所、幼稚園などと子供と家族についての情報を共有し、適切な時期に適切な機関とともに同じ目線で係わっていけるようにしなければなりません。同時にそれぞれの機関が最も身近な場所で、家族と子供の側に立った関わりが持てるように支援していく役割も求められます。
まだ移行したばかりのたんぽぽホームが、この二つの方向性を実現していくにはしばらく時間がかかるでしょう。はじめに行うべきことは、地域で訪問しやすいと考えられる子育て支援センターや子育てふれあいプラザ(のびすく)などとの協力です。子育てに不安を抱えている家族がまず訪れるのは誰でもが行くことができる子育て支援機関だと考えられます。また、地域の子供たちの居場所である保育所や幼稚園、児童館などと協力していくことです。そこには、発達に不安を抱えた家族と子供がいるはずです。地域の様々な居場所においても家族と子供の側に立った支援が必要とされているのです。
たんぽぽポホームには、それぞれが地域にあって、子供とその家族が安心して暮らせるような支援を行うこと、様々な支援機関や専門機関との協力体制を構築しどこに居ても適切な支援を受けることのできるようにしていくことが求められるのです。その期待にこたえるためにはコーディネートする役割がある地域相談員の体制も力量も十分ではありませんが、まず一つ一つの実践を積み重ね、少しでも地域からの信頼を得られるよう努力していきたいと思います。
今年、どの様な骨組みを組み立てることができるのか、それは一つの試練かもしれません。しかし私たちは、様々なことに真摯に向き合い、逃げることなく挑戦していかなければならないのです。「猪突猛進」は猪を譬えとした言葉です。たぶん今年の年賀のあいさつでは多く語られる言葉となるでしょう。見境なき猛進は混乱を招くかもしれませんが、目標に向かって走りつづけるのであれば、この法人のあるべき姿を現しているともいえるでしょう。
今年も皆様のご理解とご指導をいただけるようお願いいたします。
令和2年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会 理事長 細井 実
2018年(平成30年)
新年のごあいさつ
皆さん、新年あけましておめでとうございます。
平成30年、西暦2018年が始まります。
今年は「戌」年です。動物では「犬」があてられています。「戌」という字は「一」と「戈」からなり、刃物で作物を刈り取ってひとまとめに締めくくり、収穫することを意味すると言われています。(漢字源より)
平成という元号は来年の4月30日までと決まっています。この時代の区切りを前にして、多くのことが刈り取られるように、また締めくくりのようにして語られる年となることでしょう。ただ収穫として多くのことが語られるとするならば、そのことは同時に新しい時代の種を得ることでもあります。今年は、きっと時代の成果や反省と悔恨が語られるだけではなく、それを礎として、未来への夢と希望が語られる年となるでしょう。
当法人としては、何を収穫しどのような種を得たらよいのでしょうか。
今年は、昨年移行した袋原たんぽぽホームに引き続き、他の5か所のホームが同時に「児童発達支援事業」から「児童発達支援センター」に移行します。「センター」に移行する目的は地域への関わりを強くすることにあります。発達に不安のある子供とその家族が地域で安心して暮らせるように支援していくことは、たんぽぽホームの大きな役割です。そのため子供の姿を家族と共有し、地域で自立し穏やかに子育てができるよう支援してきました。ただ地域には保育園や幼稚園、児童館や子育て支援センター等多様な居場所があり、子供たちはたんぽぽホームだけではなくそのような居場所に関わりながら育って行きます。地域で安心して暮らすためにはそのような居場所にあっても、適切な対応を得ていかなければなりません。地域との関わりを強くするとは、そのような居場所で働く保育士や教諭等が、発達や成長に課題を抱えた子供とその家族を不安なく受け入れることができるように支援することを意味しています。
また今年は「グループホーム」の設置を具体的に進めていきます。昨年には法人にプロジェクトチームを組織しました。土地所有者が建物を建設し、それを借りて設置する「建て貸し」方式で進めることとし、関係する方々との協議を開始しています。法制度上では「共同生活援助」というように、障害のある方が、複数で協力して暮らしていこうとするものです。設置する上で不可欠なことは、地域で孤立しないように、近隣の方々との様々な交流が図れるようにすることです。また本人の意思が尊重され安心して家庭から巣立っていけるように支援することです。生活介護事業を行う各はげみホームは利用者との適切な関係が作れるよう努力しています。また地域の方々の様々なご支援をいただきながら施設の運営を行っています。「グループホーム」の設置に当たっては、そのような営みを生かし、安心して本人と家族が地域での共同生活を受け入れられるように支援していかなければなりません。
このように法人の当面の課題を見ていくと、刈り取り収穫すべきことは、地域との関わりの経験であると言えるでしょう。とても十分な経験があるとは言えませんが、たんぽぽホームでは卒園した子供や家族の支援を通して様々な関係者とのネットワークを築いてきました。またはげみホームでは町内会や地域のボランティアグループ等との交流を通して地域に必要な施設として受け入れられるよう努めてきました。このような経験を収穫として改めて点検し、「児童発達支援センター」への移行と「グループホーム」の設置にむけた種を得ていかなければなりません。
現実が求めるスピード感からすると種から育てる時間はないという誹りを受けると思いますが、種が無ければ育てることはできません。種が芽を出しいずれ花を咲かせるようにする、スタートの年が戌年の今年であると信じています。
また法人の事業を支えるのは、職員一人ひとりの意欲と責任感です。職員は貴重な財産であり、その能力を遺憾なく発揮できるようにしていくのが法人の責務です。福祉労働を取り巻く環境は厳しく法人だけで解決できる問題ではありませんが、少しでも働きやすくなるように努力をしたいと思います。そのため昨年度は世代間の公平性を考慮した給与体系の見直しを行いました。今年は意欲を引き出すような評価制度の確立に努めていきたいと思います。また能力向上の研修の充実や人材の計画的な確保等に今後取り組まなければならないと考えています。
法人の歩みは遅々たるものかもしれません。でも着実に前に進まなければなりません。そのためには、法人の事業に少しでも関心を寄せられる方々を始め広く市民の皆様のご支援が必要となります。
新しい年を迎えるにあたり、今年が未来への夢や希望を語ることができる年となるよう、職員一丸となって取り組む覚悟です。
今年もどうかよろしくお願いいたします。
平成30年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会 理事長 細井 実
2017年(平成29年)
新年のごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。2017年がスタートしました。
今年は酉年です。漢和辞典によると酉の文字は8月を表し、この月にきび(黍)が成熟して芳香な酒を作ることができることから、成就するという意味があるということです。成就するということでは、当法人は54年という長い歴史がありますが、まだたくさん成し遂げなければならないことがあると思います。
成就するという観点から5つほどお話しをしたいと思います。
一つは児童発達支援事業の児童発達支援センターへの移行ということです。支援事業が積み重ねてきた実績を活かし、地域への支援機能を強化しようとするものです。社会経済状況や価値観等が転換していく中で、親や子の抱える問題が複雑化し、今までの育児や障害へのアプローチでは対応が難しい問題が増えています。また問題の把握や改善を図るためには生活の場である地域への継続的な関わりが必要になっています。地域支援の実践は、複雑化する問題を理解し支援の方法を模索する上での知識を学び、経験を積む良い機会となるでしょう。また地域の様々な関係機関、関係者とチームを組むことで対象家族へのきめ細かな対応を可能にします。センター移行は仙台市が進めているのですが、当法人として支援事業の発展と捉え積極的に進めていきたいと思います。
二つは生活介護事業における地域支援機能の強化ということです。生活介護事業では、それぞれの個性や障害に配慮しながら、日中生活を充実させるための多様な活動をしています。また利用者の意志を尊重しきめ細かな対応をするように努めています。多くの方は家族のもとから通っていますが、利用期間の長期化等から家族の高齢化が進んでいます。また自立を図るためには、地域で一人の住民として生活できるよう支援することが望まれています。このような観点からすでに多くの事業者がグループホームを設置してしますが、当法人でも、生活介護事業での実績を生かし、利用者の生涯にわたる支援を行うためにグループホームの設置を進めていく時期が来ていると思います。
三つは社会福祉法人の改革に積極的に取り組んでいくということです。社会福祉法人は公の支配に属する福祉事業を行う主体として設置されたものですが、事業の規模や経費の急速な伸長を背景として、法人経営上の歪が表れてきました、それが昨今の不祥事に現れているのだと思います。社会福祉法の法人に関する条項が抜本的に改正され、今年の4月には完全に施行されます。その一番の目的はガバナンス(統治能力)の強化にあり、評議員会、理事会、監事等運営組織の役割と責任が明らかにされ、相互の牽制作用が働くようになります。また経営情報の開示や財務規律の強化も図られます。当法人は社会福祉法人としての責務を自覚し、健全な経営に努めてきましたが、法改正を契機に利用者、その家族、市民の皆さまにさらに信頼されるよう改革を進めていきたいと思います。
四つは人的資源の育成と組織の健全な発展を目指していくということです。社会福祉事業ではともすれば使命感が先行し、それを支える組織の健全な発展が後回しになってきました。昨年末には大手広告代理店の過重な時間外労働の問題や市内の更生保護法人でのパワーハラスメント事件等が報道されましたが、これらを他山の石としなければならないと思います。法人の財産は職員です。職員が意欲を保ち、利用者に寄り添うことで事業は成り立ちます。職員の一人ひとり、管理者の一人ひとりは改めて自己点検し、能力の研鑽に努めるとともに法人の一員としてお互いに信頼しあうことが大切です。法人としても職員の育成や働きやすさへの配慮に不断の努力をしたいと思います。
五つは酉年がとりの年と言われることからの連想です。干支では鳥は鶏ですが、ここでは普通の鳥を考えてください。鳥はいうまでもなく空を飛びます。その目は空から地上を見ています。そのような鳥の目が示唆するものは2つあります。
一つ目は高いところから見下ろすような視点が必要であるということです。初めに当法人には成就することがあると言いましたが、成就するということは必ずしも完璧に成し遂げるということではありません。目標に向かって全体的な枠組みや道筋を明らかすれば良いのだと思います。そのことを忘れて、些細なことや目の前のことにこだわり、隘路に入ってしまっては成就する道は遠のきます。鳥の目からということは、より高い目線で全体を見、目標を見失わないようすることが大切だということを意味しています。
二つ目は高いところから見られているという意識が必要であるということです。成し遂げるということは、自己改革から始まりますが、変革は己のためだけにするものではありません。法人事業の、また地域の福祉の、さらには社会福祉全体の改革へとつながり、市民社会にも影響していきます。これを逆にたどれば市民生活の変容や現状に対応しながら事業を常に見直し改革することが求められるということです。また見られているということは、監視されているということであり、法令等を遵守し己を律しなければならないということでもあります。法人は利用者、家族、さら地域住民と常に出会っています、また行政や関係機関を通して広く市民とも出会っています。鳥の目を意識するということはこのような方々の視線をいつも忘れずに自分自身を律し、変革に取り組んでいくということです。
新しい年を迎えるということは、いつも心躍るものです。酉年は鳥のように飛躍する年であると言われています。当法人も飛躍できるように気持ちを入れ替え、職員一丸となって事業の進展に努めます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
2017年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会 理事長 細井 実
2016年(平成28年)
理事長 あいさつ
皆さんこんにちは。
小池英一理事長の退任を受け、10月8日に理事長に就任いたしました。
この法人が昭和38年(1963年)財団法人宮城県小児麻痺福祉協会として創設されてから実に53年の月日が経っています。その間に6人の会長・理事長が就任されそのご努力によって今日の法人が作り上げられてきました。
それらの先人に及ぶことは到底できませんが、その歴史を繋ぎながらさらにこの変転、混迷する時代にふさわしい法人像を描いていくことが私の責任であると考えています。
法人の最も重要な使命は、様々な困難や苦悩を抱えながらこの法人の戸をたたいてきた方々を、「生きていて良かった」と日々感じられるように支えていくことにあります。
そのためには職員が、戸をたたく音を聞き逃さず、やさしくその戸をあけ、訪れた皆さん一人ひとりの願いは何かを問い、それが叶うように真摯に努力してくことが必要です。その努力が無くしては、法人の存在意義は無いと思います。
また法人として、多様化する障がい像や複雑な生活環境などを目のあたりにして、たじろぐことなく、どのようにすればその問題に立ち向かうことができるのか必死に考え、考えたことを実行していかなければなりません。そのためには、職員がその資質を研鑽していくことが求められますが、同時に様々な専門性や蓄積された経験や知識を動員して組織として対処できるよう法人自体の機動力を高めていく必要があると思います。
さらに、どのような障がいがあっても、それぞれが生活するその場所で安心して暮らしていくことが望まれています。そのことが「生きていて良かった」と言える原点でもあります。法人の経営する施設はその地域の貴重な支援の拠点となっています。改めてその機能を点検し、地域での生活をどのように支えることができるのか考えていく必要があると思います。
わが国の福祉や医療は、流動する社会経済情勢に翻弄され、いつまでも落ち着く場所を見いだせずにいます。改革の名のもとに行われる法制度や行政対応の変化が、支援を必要とする方々を困惑させ将来への不安を抱かせています。法人の力が及ぶものではありませんが、支援を求めている方々が感じている不安を受け止め、その声を基にして福祉や医療の充実や安定に少しでも貢献していくことが求められるでしょう。
法人を取り巻く環境は日々変化し、法人としての適格な対応が求められていますが、根幹となる使命は揺らぐものでありません。職員一人ひとりが、自らの職務と責任を自覚し、日々の業務で見せる姿勢を通して、利用者とその家族、さらに地域の方々の信頼を得ていくことが、最も大切であると思っています。法人を気遣って下さる多くの方々のご理解とご協力をいただき、法人が更なる信頼を得ることができるよう職員と共に歩んでまいりたいと思います。
社会福祉法人仙台はげみの会
理事長 細井 実
2026年(令和8年)新年のごあいさつ

あけましておめでとうございます。
今日から令和8年、西暦2026年です。
東日本大震災から15年となる年です、皆さんはどんな感慨をもって新しい年をむかえられたでしょうか。
仙台はげみの会が発足したのが昭和38年(西暦1963年)です。財団法人認可の日は8月5日ですから、その日からは63年目となるわけです。人間の限りある一生と、この社会の時間の経過を比較することはできません。それでも、人間でいえば高齢者と呼ばれる年まで年数を重ねここまで来たわけです。それも平穏で、平たんな道を歩んできたわけではありません。障害福祉と言う世界があるとするならば、
私たちはこの世界に何をしてきたのか。
私たちはこの世界で何をしているのか。
私たちはこの世界で何をしていかなければならないのか。
そのような問いを重ねながら、様々な課題のあった凸凹道を歩み、63年の月日がたったわけです。それは過去を振り返りながら、現在を点検し、未来を構想していくというありふれた問いかもしれませんが、障害者を取り巻く社会の不条理と不如意と闘い続けるための問いなのです。そのような闘いには勝者も敗者もありません。それは誰もが、どのような境遇にあろうとも、どのような状態にあろうとも、平等に差別されることなく生きていくことのできる社会とするための闘いです。
この法人には、今までそのような闘いを続けるための言語化された理念、私たちの過去と現在を明らかにし、未来へと導く言葉が無かったのです。無論だから今までさまよい歩いてきたというわけではありません。常に皆で問い、考え、実行してきた結果が現在の姿です。ですから、いままで成し遂げてきたことを無視して、新しい言葉を紡いでいくわけではありません。
昨年の10月24日の理事会で、法人の理念を定めました。
私たちは、この街に初めて灯された希望の「灯」であることを忘れない。
どんな障害があっても、
誰もが「私の居場所」はここにあると心から思えるように。
「ありのまま」を、「はげみ」を未来へとつなぎ、共に歩む。
この法人がこの街で初めて障害のある子どもと保護者が集える場を作ったという過去を誇りとして、現在につなぐこと。
そして現在に至るまで、どのような障害があろうとも、自分らしさを肯定して生きていける「居場所」づくりをしてきたこと。
その「居場所」づくりを続け、誰もが「ありのまま」であることを認められ、より良く生きたいというそれぞれの「はげみ」を求めることのできる未来。そのような未来を、障害ある人々と共に創造していくこと。
理念にはこのようことが託されています。この理念は、法人のアイデンティティを語る言葉であり、法人が目指すべきこと、しなければならないことの明示であり、地域と絆を結び、誰もが差別されることなく生きていける社会となるように闘い続ける決意の表明です。
私たちは、この「理念」を 常に胸に抱き、またいつでも言葉で語れるようにしながら、法人の一員としての自覚をもち、日々の業務に努めなければなりません。保護者や利用者にもこの理念の持つ意味を考えながら語りかけ、伝わるようにしてほしいと思います。
今年も挑まなければ課題があります。
仙台市では、児童発達支援センターの指定管理者を令和11年度から公募で選考するという方針のもと、「療育支援体制のあり方」の検討を行っています。(現在は非公募で決定されています。)
たんぽぽホームはアーチル(発達相談支援センター)と共に、就学前の発達に不安のある子ども、障害のある子どもと保護者の支援を担ってきました。アーチルでの相談を通して早期の診断や評価を受けた子どもと保護者を受け入れ、療育支援(本人支援)と保護者支援を行い、保育所や幼稚園、認定こども園への入園、あるいは就学へと結びつけているのです。発達の特性に合った環境整備等により「子どもが育つ」ことを、また子どもの特性の「ありのまま」を認め、本人に合った育て方を知ることで「保護者が自立していく」ことを支援しているのです。それは就学前の療育支援体制に不可欠の過程であり、誰もが知り、経験することが望まれる過程なのです。
しかし、「療育支援体制」を取り巻く環境は大きく変化しています。
最も大きな変化は、保護者の就業意欲の向上です。育児と仕事の両立支援は、法改正による改善が進んでいます。障害のある子どもを持つ親は働くことができないという状況は差別につながるとも言えるのです。しかし、現在たんぽぽホームが実践している支援の機会を保護者の就業によって得られないということもまた、適切な支援を受けられないまま子どもと保護者が過ごしてしまうという大きな問題になります。
次に考えられる変化は、子どもと保護者が共に通うことへの抵抗感の増大です。保護者の生活様式の多様化と言うか、子育てに生活をささげるような生き方ではなく、育児しながらも自分らしく生きたいという思いが広がっているのだとも思います。その思いは障害のある子どもを育てている保護者であっても変わらないということです。子育ての負担を軽減するような政策が進められている中で障害のある子の保護者だけ例外であるとは言えないでしょう。
次にあるのは、児童発達支援事業所の増大です。平成24年の児童福祉法改正により従来の児童デイサービスや通園施設が児童発達支援事業となりましたが、その後株式会社やNPO 等の参入が相次いでいます。規制緩和により参入障壁が無くなったこと、小規模で施設・設備等への投資が少なくて済むこと、運営費が給付費支給で保障されていること等がその要因です。通園施設は法改正当初より、また、たんぽぽホームは平成30年に児童発達支援センターとなり、地域の中核的支援施設と法的には位置づけられています。ただ仙台市ではアーチルとたんぽぽホームが一体となって、地域の中核機能を担っているため、利用者への直接的な支援を担っているたんぽぽホームと、児童発達支援事業との差別化が難しいというのが現状です。ただたんぽぽホームでは児童発達支援センターとなってから地域の子育て関係機関への訪問や相談、研修等に取り組む地域支援を積極的行うことで、中核機的機能を高めています。
また令和6年に定められた「児童発達支援ガイドライン」では、児童発達支援センターの中核的役割が示されています。
・幅広い高度な専門性に基づいた発達支援・家族支援機能
・地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
・地域のインクルージョン推進の中核としての機能
・地域の障害のあるこどもの発達相談の入り口として幅広い相談機能
これらの機能をアーチルとの役割分担でどのようにして、発揮していくかも大きな課題と言えるでしょう。
更にいくつか挙げるとすれば
・アーチルの相談までの待機期間がいくらか改善されたとはいえ未だ問題であること。
・アーチルによるセルフプランで給付費を決定している現状をどう考えるのか。
・保育所、幼稚園等に通いながら早期の療育を受ける併行通園へのニーズがあるが、児童発達支援センターでは応えていない。(児童発達支援事業所では実施している。)
・医療的ケア児の受け入れや重度障害児の受け入れが進む特別支援保育との連携。
「療育支援体制のあり方」とは、以上述べてきたような様々な課題に対処し、「新しい療育支援体制」を構築していくことです。
令和6年6月の仙台市議会で、アーチルを各区に設置すべきではないかと言う議員の質問に仙台市長はこう答えています。
「南北二つのアーチルを含めた就学前療育支援体制のあり方について検討してまいります。あわせまして、関係分野との連携に努めながら、こどもたちが健やかに育つインクルーシブな環境の充実に取り組んでまいる考えでございます。」
児童発達支援事業所数の増大がその主な要因と考えられますが、児童発達支援センターの利用者者が減少しているのは確かです。ただそれを是として、児童発達支援センターの縮小や廃止をめざす、規模縮小や経費削減のための見直しであってはなりません。
また児童発達支援センターだけが課題に向けて対応していくということではないでしょう。今まで療育支援体制を支え、担ってきたアーチルと児童発達支援センターが現状の枠にとらわれず一旦ぞれぞれの機能を棚上げし、今後の連携と協力の考え方を示し、「新しい療育支援体制」を構築しなければならないのです。
見直しの要諦は、市長の言葉で言うならば「こどもたちが健やかに育つインクルーシブな環境の充実」ということです。私なりに言い換えるならば、仙台市民にとってなにが最善の利益をもたらすのかということです。見直すことで障害のある子どもと保護者への支援が後退することはゆるされません。今はやりの言葉で言えば「障害児と保護者ファースト」でなければならないのです。
次に、法人にとって大きな課題はグループホームの設置ということです。既にTagomaruハウスを設置していますが、定員20名は満たされていて、新規の入居希望に応えることはできません。生活介護施設である3か所のはげみホームの利用者に昨年アンケートを実施したところ。19名の入居希望がありました。一番新しい国見はげみホームが平成22年(2010年)開所ですから当初からの利用者は30歳代半ばになります。まだ若いと言えるかもしれませんが、そろそろ家庭から出て自立して生活することが本人からも家族からも望まれる年齢でしょう。元気なうちは頑張るという保護者もいますが、いずれは介護が難しくなるわけで、利用者の将来の生活が不安になるころでもあるでしょう。そして、何よりも、利用者が、家族から自立し、自分なりの考えや思いをよりどころにして地域で自立した生活をすることが、人生そのものを豊かな経験に満たされたものにしていくのです。更にそのことが、この社会を差別のない平等な社会へと変える礎となるのです。グループホームは利用者の「「ありのまま」を、「はげみ」を未来へとつなぐ「居場所」なのです。
また最近は保護者の疾病や高齢化で、グループホームへの入居が喫緊の課題となることも増えています。夜間の支援が最優先で、生活介護等日中の支援の場所はグループホームに入れるかどうかで選択するということも起こっています。
法人の責務として、利用者の未来を保障するために、グループホームの設置が急がれるわけです。
しかし、いくつか課題があります。
一つは設置するための資金計画です。最近の建設資材や人件費は高騰していて、その傾向は収まることを知りません。事業規模の決定、用地の取得、造成、設計、建設と進むわけですが、総事業費の見積もりと資金の調達方法を早期に確定しなければなりません。関連する手続きや窓口も複雑で多数あり、それらを専門知識のある方の支援を得て進めていくことも必要です。そして法人の資金力にふさわしい建設可能な計画を作成し、早期に着手するのです。
二つは設計に関わることですが、入居予定者の特性や生活様式等に応じた過ごしやすい環境が備わった建設を行うことです。利用者にとってはそこで一生を過ごすわけですから生活しやすく、安全でかつ心地良い場所でなければなりません。早期に入居予定者を決定し、意思決定支援も行いながら、一人ひとりに合った居住空間を創り上げるのです。
三つは人材の確保です。福祉人材が決定的に不足しています。そのような中で新しいグループホームの職員をどのように得ていくのか、多くの困難があります。現在法人にワーキンググループを設置し計画全体の作成や実行を担うこととしています。グループのメンバーには実際に運営するにあたっての核となる人材となることを期待しています。実際に開所する時には多数の人材が必要となりますが、法人全体での人材確保を含めた人材育成計画を考えていかなければなりません。政府によって福祉人材の処遇改善が飛躍的に進み、人材が得られるようになることを期待しています。
四つはこれも資金に関わることですが、運営資金の確保です。現在のTagomaruハウスはホームヘルパー事業の利用で収支相償となっています。建て貸し方式ですので賃貸料が支出には含まれています。新しいグループホームは法人で建設することにしているので、資金の融資を受けることになります。と言うことは借入金の返済が発生することになるわけです。借入規模によって金額が決まりますが、返済をスムーズに行うためには他の事業の収支が改善され、借入金返済が余裕をもって行えるだけの資金的体力が求められます。
五つは入居予定者の家賃等負担です。建設費がかかれば。普通であれば入居者の家賃が上がることになりますが、障害のある人が支払うことのできる金額は、障害者年金で負担できる範囲となるでしょう。Tagomaruハウスで設定している家賃より高くなっては負担ができないということになるかもしれません。年金額を超える場合は保護者負担が生じるようになります。また同じ法人が運営するのに家賃が異なるということは不公平だと言えるでしょう。計画が確定した段階で精査していかなければなりません。政府は昨年の4月から年金を1.9%増額しているといっていますが、物価高や賃金の上昇には追い付いていないでしょう。グループホームが確実に増えている中で、その家賃負担も見据えて年金の増額なり、家賃補助の拡充がなされるよう期待します。
考えれば考えるだけ課題が増えていきます。どれも乗り越えていかなければなりません。生活介護事業はげみホームの利用者と保護者のことを考えれば、それほど時間をかけるわけにもいきません。課題があればあるだけ乗り越える喜びが増えるのだという気概をもって、皆で知恵を出し合い、考え、議論しながら、「未来につなぎ」、それほど遠くない「未来」に、新しいグループホームを設置していきたいと思います。
次は、上記の「四つ」という課題に関係しますが、生活介護事業はげみホームの経営改善です。法人の経営安定のためには。生活介護事業の収支改善がなされなければなりません。法人本部の収入は主に生活介護事業からの繰入金で賄われています。また積立金の財源も多くが依存しています。法人の運営の基盤となっていると言っても過言ではないでしょう。
しかし、給付費が伸び悩んでいるという背景があるにしても、収支が赤字となっている事業所があるわけです。ここ数年で給食調理の専門事業者への委託、パン製造販売のベーカリー事業の廃止、職員の適正配置、利用者の障害等級の見直し、利用者の確保等の努力をしてきました。実施に当たっては職員と利用者、保護者の十分な理解を得て進めてきました。しかしいまだに努力が足りないのかもしれません。
無論、利用者への支援の質が下がるような方策を講じることはできません。また職員の改善への意欲が醸成され、積極的に努力する姿勢が無ければ実施することはできません。
次は、すでに一部導入が進んでいますが、法人の事務の電子化を利用者支援の質向上につなげるということです。職員の勤怠管理の電子化や事務決裁のワークフローによるペーパーレス化が当面進められます。事務が効率的に処理されることで生まれる時間や軽減される精神的負担を有効に活用し、支援計画の作成にあてたり、支援の内容を充実させたりすることが期待されています。今後電子化の範囲が広まり、職員間、あるいは職員と保護者との情報共有、保護者支援に生かしていくこと等などが期待されます。
サポートセンターTagomaru、Tagomaruハウスでは、令和元年の開設以来、法人の積立金の半額近くを投入して、事業が安定するまでの資金不足を補ってきました。グループホームの定員が埋まり、土日も利用されるようになり、ホームヘルパーの利用も進むことで経営は安定し始めています、ただ、取り崩した積立金をもとに戻すような勢いはありません。それは法人全体で考えることではあるでしょう。
また新しいグループホームの設置に向けた準備の中心となり、他の事業所のリーダーとなる役割が期待されているので、そのための人員育成等の検討が必要になるでしょう。
毎年のことですが、今年もまた乗り越えなければならない課題がたくさんあります。
いずれも気を抜くことができない課題です。また時間もそれほど与えられているわけではありません。
ただ、私たちの進もうとしている道は、
「誰もが「私の居場所」はここにある」と心から思えるように。
「ありのまま」を、「はげみ」を未来へとつなぎ、共に歩む。」「道」です。
それは、この社会を差別のない、平等で平和な社会へとしていく「道」でもあるのです。
今年は午年です。午には馬が当てられます。馬は走るだけではなく、障害物を乗り越えて進みます。多くの課題を馬のよう乗り越えていく、飛躍の年となるよう祈念します。
社会福祉法人「仙台はげみの会」を支えて下さっている皆さま
法人事業を利用している皆さま、家族の皆さま
職員の皆さま
すべての皆さま
改めて、今年もよろしくお願いいたします。
令和8年元旦
社会福祉法人仙台はげみの会
理事長 細井 実